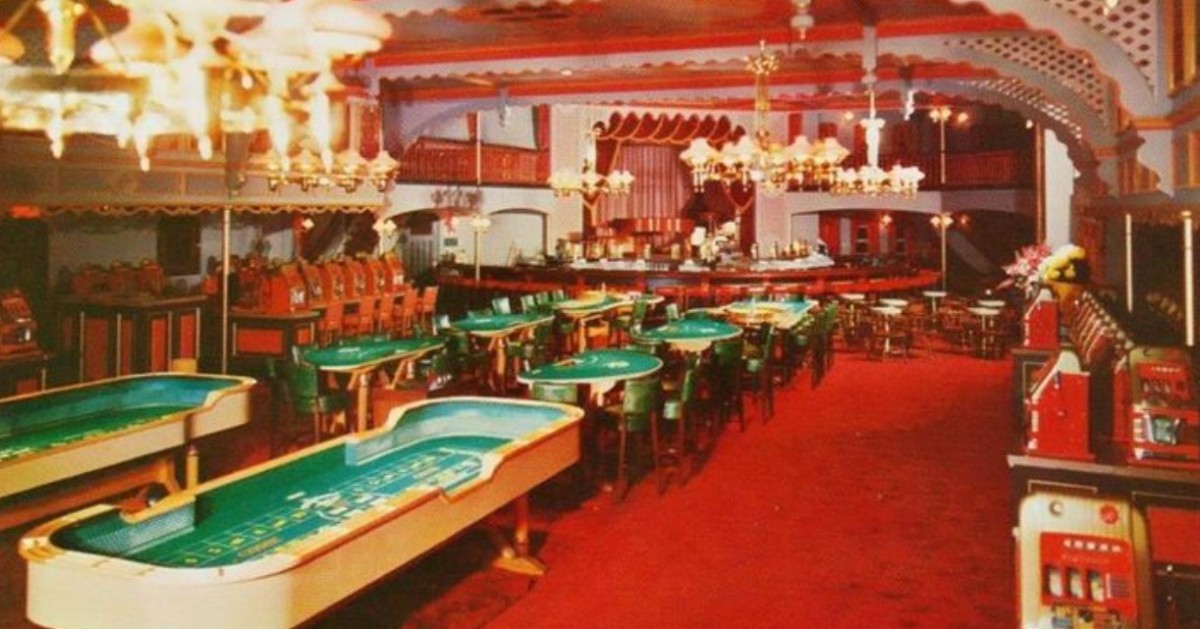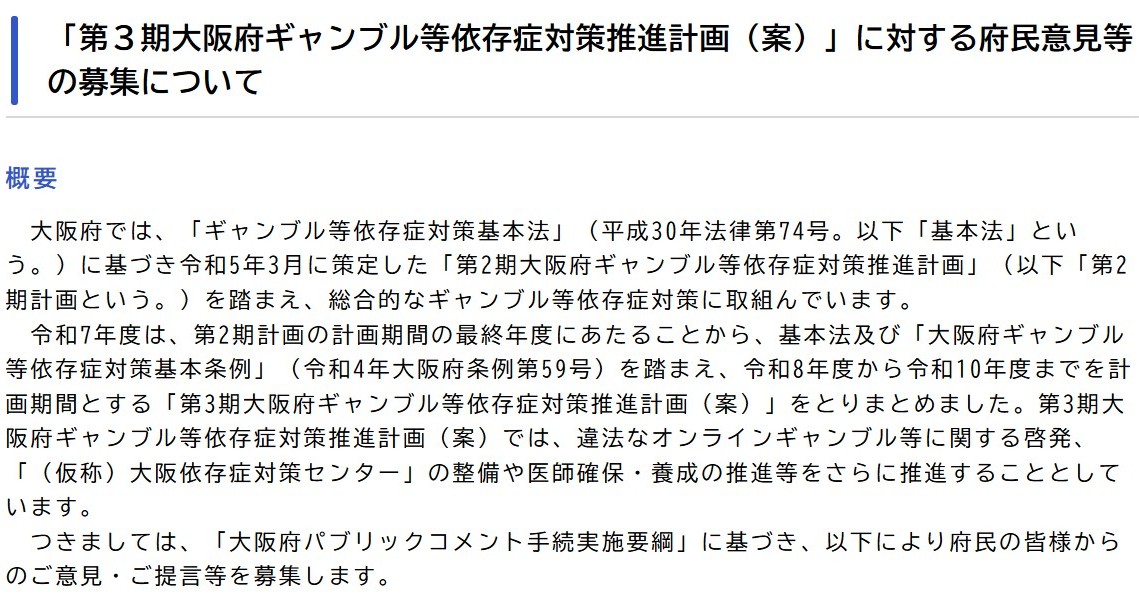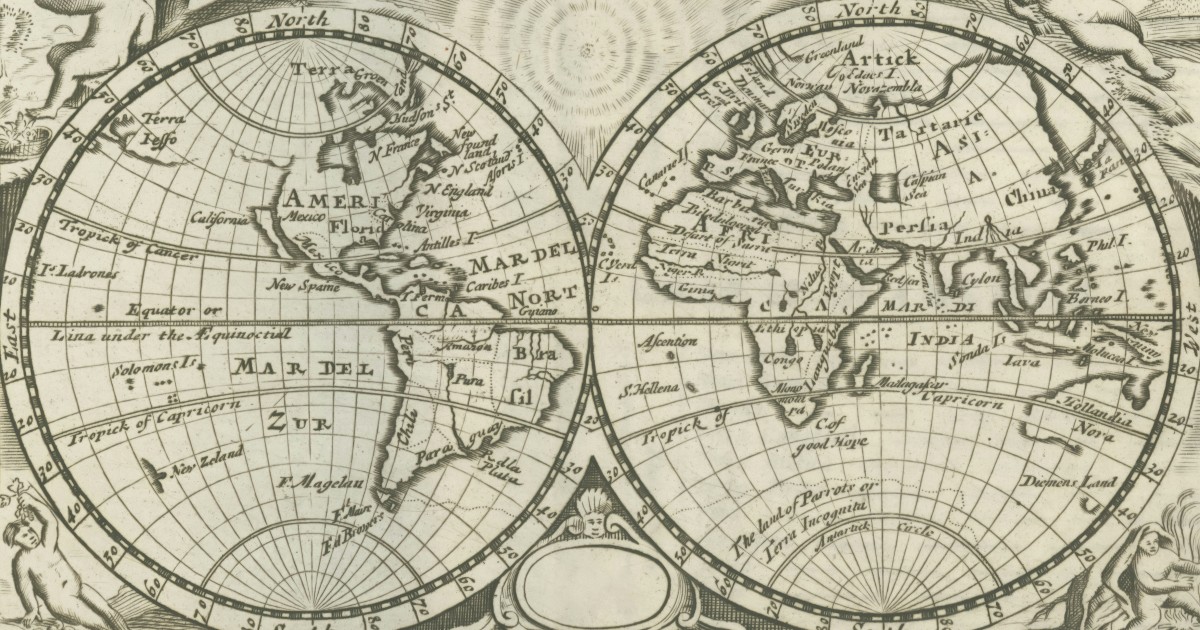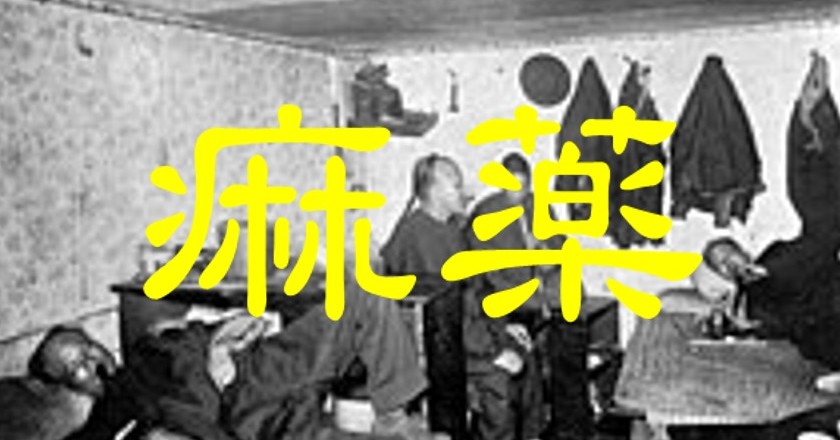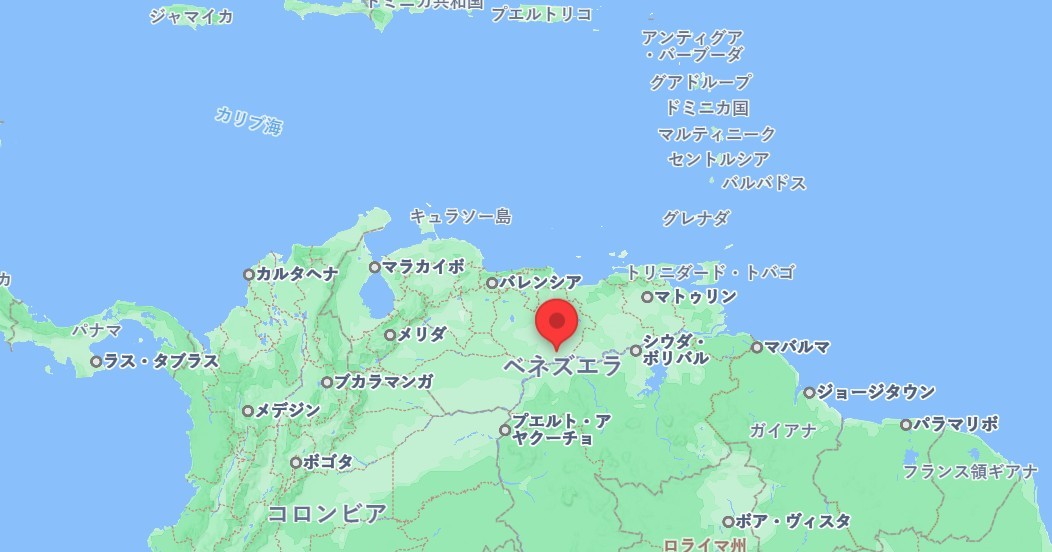薬物禁止法(ゼロ・トレランス)からの訣別

1. はじめに
世界の違法薬物使用者は推定で2億数千万人に達しているといわれ、違法市場の規模も拡大している。さらに刑罰を背景にした薬物との戦いは、薬物使用者の大量投獄、違法な闇市場の活性化、HIVやC型肝炎などの感染症の蔓延、都市での薬物に起因する暴力、人権侵害などを引き起こし、国際的な開発目標にも悪影響を与えている。
2. 国際的な薬物規制体制の歴史
東アジアにおける阿片禍の危機的経験から、20世紀になって国際的な薬物規制が始まった。当時の薬物問題とは、正当な医薬品の横流しが主な原因であり、この時期に作られたシステムは、薬物の取引を規制するために作られた多くの条約で構成されていた。
史上初の国際協定である1912年の「ハーグ・アヘン条約」は、アヘンとコカの国際取引を規制するためのものであった。1936年の「危険薬物の不正取引の防止に関するジュネーブ条約」は、不正薬物の生産(栽培)と取引を初めて国際犯罪として規定した。当時の世界的な大国は、どの物質を禁止法に含めるかについて交渉したが、タバコとアルコールはリストから除外された。両物質とも依存症につながるが、交渉の中心にいた植民地大国にとっては文化的・社会的、経済的に重要な物質であったため、違法薬物取締制度の対象外とされたのである。
第二次世界大戦後、国連は戦前に構築された国際的な薬物規制体制をいっそう強化するために、それまでの条約を一本化するための交渉を開始した。こうして出来たのが1961年の「麻薬に関する単一条約」(単一条約)である。
単一条約の目的は、医療や科学研究のための医薬品へのアクセスを確保しながら、薬物の非医療的(娯楽的)使用と依存症を撲滅することを目的としていた。しかし単一条約は、娯楽目的での薬物使用を「悪」という異例の感情的な言葉を使って非難し、刑罰によってこれを撲滅することに焦点を当てていたため、この条約を契機に世界の薬物政策はより厳格な禁止法(ゼロ・トレランス=不寛容主義)へと向かっていった(単一条約には世界中のほとんどの国が加盟しており、条約は加盟国に条約の趣旨にそった国内法の整備を義務づけている)。
単一条約の内容で重要なことは、依存性の強弱と娯楽用への転用可能性を組み合わせて規制措置の強弱を決める「スケジュール」の仕組みを作ったことである。これにしたがって、アヘンやコカ、大麻などの「麻薬」規制が決められた。その後、1971年の「向精神薬に関する条約」によって向精神薬(MDMA、LSD、シロシビン、マッシュロームなどの合成麻薬や植物由来の麻薬)が規制された。しかし、これらの規制基準は、医療目的での入手の可能性に関連するものであり、科学的な分類にもとづくものではなかった。
これらの法的仕組みは、1988年の「国連麻薬及び向精神薬不正取引防止条約」によって補完され、薬物使用の犯罪化が加盟国でさらに進められ、国境を越えた薬物取引とマネーロンダリングに対抗するための法的手段が整備されていった(わが国では「麻薬特例法」が制定された)。
こうして世界的な薬物取締体制は、需要の削減、供給の削減、そして国際的な司法協力という3つの基本戦略を軸にした刑事法的手段を背景にしてさらに強化されていった。
3. 薬物戦争の失敗
1998年の国連総会(UNGASS)は、10年以内に地球上から薬物をなくすという目標を掲げたが、その後も薬物の流通と使用は減少しなかった。さらに2006年、カルデロン政権によってメキシコの薬物政策が軍事化されたことによって、中南米諸国の治安が悪化し、国際社会では薬物政策の見直しを求める声が強まった。そして2009年には、地球上から薬物を根絶するというUNGASSの目標は、技術的・政策的に実現困難であることが意識されだした。
2016年のUNGASSでは、人権尊重やハームリダクション(害の削減)など、新たなアプローチの方針が加えられた。ロシアやイラン、アジアの多くの国々は従来の禁止主義的アプローチを維持しようとしたが、カナダや西欧諸国は公衆衛生を重視した政策を推進し、現在、国際社会は薬物政策に関して二極化している。
4. 薬物戦争がもたらした社会的影響
薬物取締政策は、特に貧困層に負の影響を与えた。例えば、違法作物の撲滅政策により農民が生計を失ったり、刑務所の過密化が深刻化した。薬物関連犯罪で投獄される人の割合が増加し、世界の囚人の5人に1人が薬物犯罪、しかもその多くは薬物の単純所持罪によって投獄されている。
さらに、薬物の使用が犯罪化された結果、使用者は地下に潜って闇で薬物を求め、注射器の共有が増加し、HIVやC型肝炎の感染率が上昇した。また、禁止法の影響で規制薬物へのアクセスが制限されたことで、世界中のモルヒネの9割が先進国で消費され、貧困地域のおびただしい人びとが疼痛緩和医薬品を十分に利用できない状況に陥っている。
5. 薬物政策とスティグマ
薬物戦争の激化がもたらした負の影響に、薬物事犯に対する「スティグマ」の問題がある。
(1) スティグマとは
スティグマ(stigma)の語源は、古代ギリシャ語で「刺し傷」や「烙印(焼き印)」を意味し、当時はこれが奴隷や犯罪者の識別に使われていた。現代では、社会的な不名誉や偏見の象徴として使われる。薬物との関連でいえば、権威ある機関によるレッテル貼りがスティグマの一因になり、とくに薬物依存や犯罪歴などに関するスティグマが重要である。
(2) スティグマの社会的影響
スティグマには、社会構成員の逸脱行動を防いだり、社会的な同質性を高めることで構成員の結束を高めるなど、プラスに働く面があることは否定できないが、問題になるのは、スティグマによって個人が自尊心を損なうことや社会的機会が制限されることであり、スティグマが差別や偏見を生み出す点である。薬物使用者に対するスティグマは特に強く、医療機関や警察などの場面で顕著に現れる。その程度は社会的な文脈によって次のように変化する。
-
責任の所在:薬物依存が道徳問題や自己責任(性格の弱さ)と見なされると、より強いスティグマが生まれる。
-
危険性の認識:社会が薬物使用者を危険とみなすほど、スティグマは強くなる。
-
社会的距離:社会が薬物使用者と距離を置くことで、スティグマが固定化される。
たとえば医療従事者の多くは、薬物依存者に対して否定的な偏見を持ち、適切な医療を提供しないことがある。特に、疼痛管理の際には「薬物を求めているだけ」と見なされ、適切な鎮痛薬が処方されないケースもある。
また、薬物使用者の多くは、治療を受けることで「薬物依存者」として認識され、刑事司法的次元で扱われることを恐れ、治療を避ける傾向がある。結果として、治療を受ける機会が減少し、依存からの回復が難しくなる。
さらに薬物使用者は日常的に警察と対立しやすく、路上での職務質問や所持品検査の対象になりやすい。社会的には「犯罪者」として扱われ、警察からの不当な扱いや暴力を受けることもある。こうした経験が薬物使用者の社会的孤立を深める要因となっている。
(3) とくに薬物と警察との関わりについて
薬物使用じたいが厳罰化されているため、薬物使用者は日常的に警察と対立する状況に置かれている。警察は薬物使用者を「犯罪者」として扱い、彼らが正当な理由で外出している場合でも、無理やり拘束したり不当に扱ったりすることがある。路上での職務質問や所持品検査では、薬物使用者が狙い撃ちにされることが多く、公共の場で辱めを受けることもある(とくに有名人の場合)。警察の対応はしばしば強制的であり、暴力的である。これにより、薬物使用者はさらに社会から孤立していく。
(4) スティグマを軽減するために
スティグマを減らすためには、以下のような取り組みが必要である。
-
教育と意識改革:一般市民や医療従事者に対して、薬物依存が「病気」であり、適切な治療と支援が必要であることを周知する。
-
言葉の見直し:「薬物依存者」ではなく、「回復を目指す人」といった表現を使うことで、偏見を軽減する。
-
治療へのアクセス向上:薬局や医療機関での差別を防ぎ、誰もが適切な治療を受けられる環境を整備する。
6. 結論
(1) 薬物依存は治療すべき疾患
薬物使用者に対するスティグマは、社会のさまざまな場面で根深く存在し、医療や警察などでの差別的対応が問題となっている。スティグマを減らすためには、社会全体の意識改革が不可欠であり、薬物依存を「個人の失敗」ではなく「治療すべき疾患」として認識することが求められる。
(2) 薬物使用の非犯罪化
とくに薬物使用の犯罪化(厳罰化)は薬物使用の抑制に寄与せず、スティグマの軽減につながらず、かえって危険な行動を助長するため、薬物使用(及びそのための所持)の非犯罪化あるいは非刑罰化を進める。
(3) 禁止法から人道的アプローチへの転換
公衆衛生を優先させ、依存症や過剰摂取による死亡を減らし、予防と治療を重視するとともに、ハームリダクション制度を導入する。
(4) 禁止法の廃止と合法的な管理
現在違法な薬物を国が管理し、安全で責任ある使用を促進する。このような試みは、すでにアメリカの多くの州やカナダ、ウルグアイ、ヨーロッパで行われており、他の国々も追随しつつある。
(5) エビデンスに基づいた薬物政策を
わが国の薬物政策の基本は、処罰が治療のきっかけになるという、科学的根拠のない懲罰的断薬主義である。これが禁止法をより強化して厳罰主義に結びつき、多くの社会的問題を生み出してきた。「薬物のない世界」は実現不可能であることを虚心に認め、科学的データと監視体制に基づいた現実的な政策こそを目指すべきである。薬物統制の代替策として、ハームリダクションや合法的管理などが提案されており、欧米諸国はすでにこの方向に動き始めている。禁止法から脱却し、新たなアプローチに移行することで、より効果的で人道的な薬物政策が実現される可能性が高まるのである。(了)
すでに登録済みの方は こちら