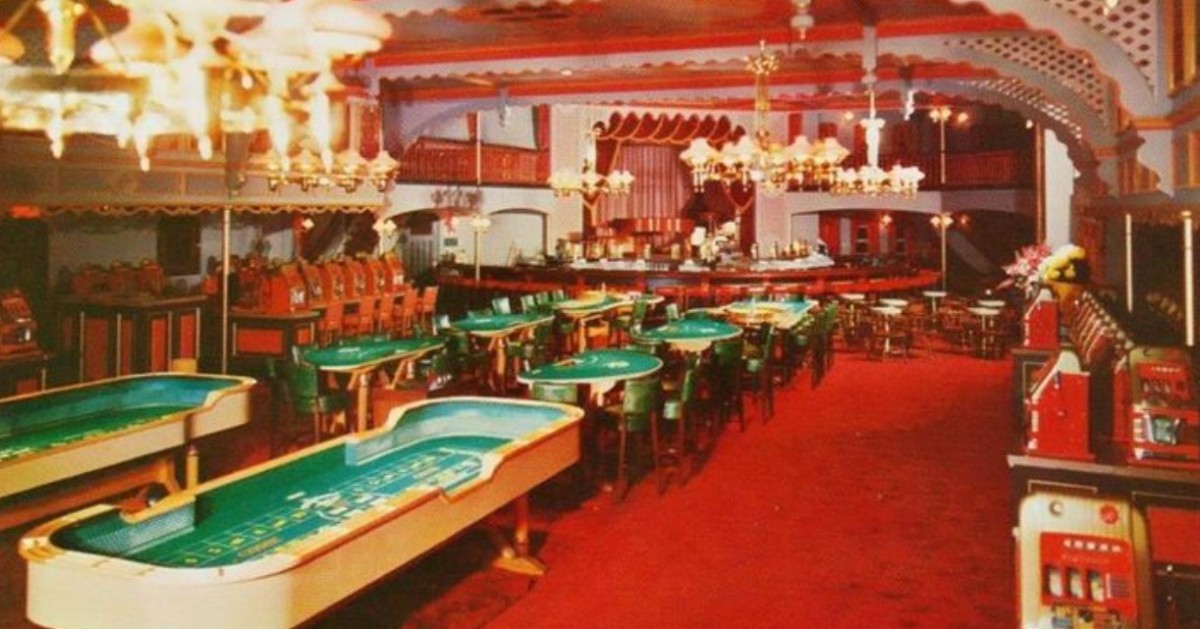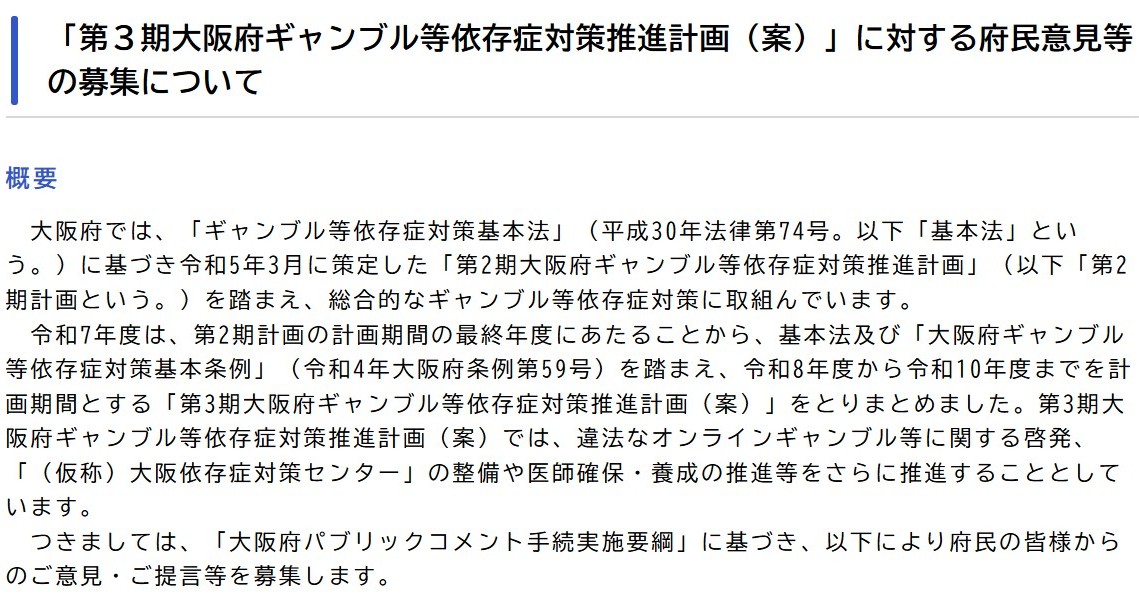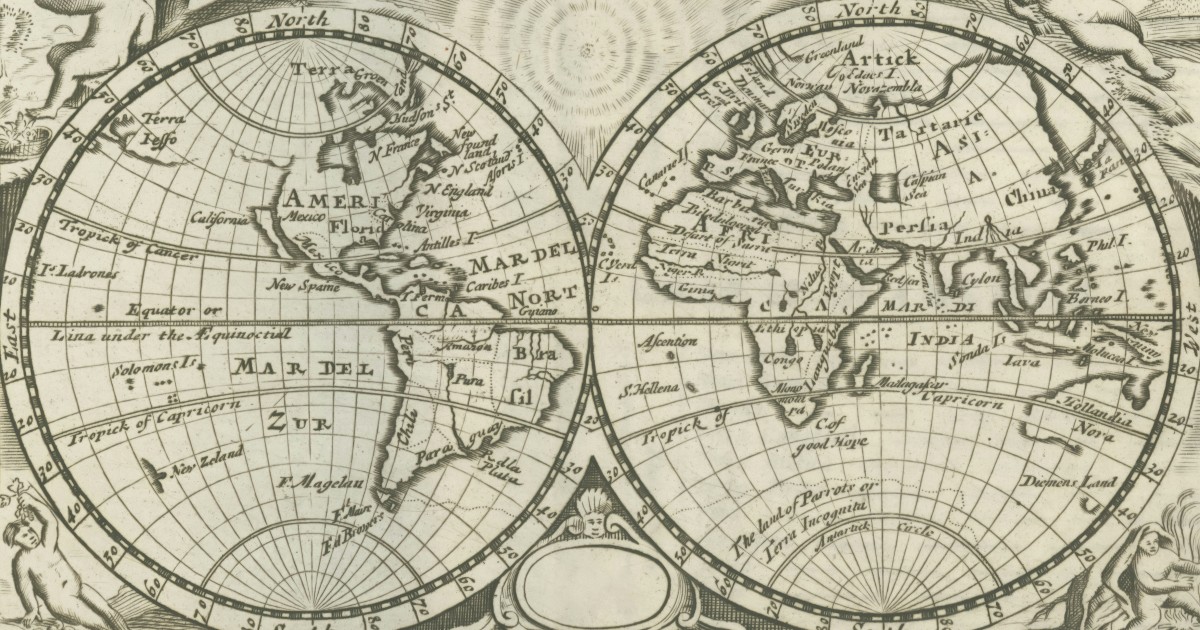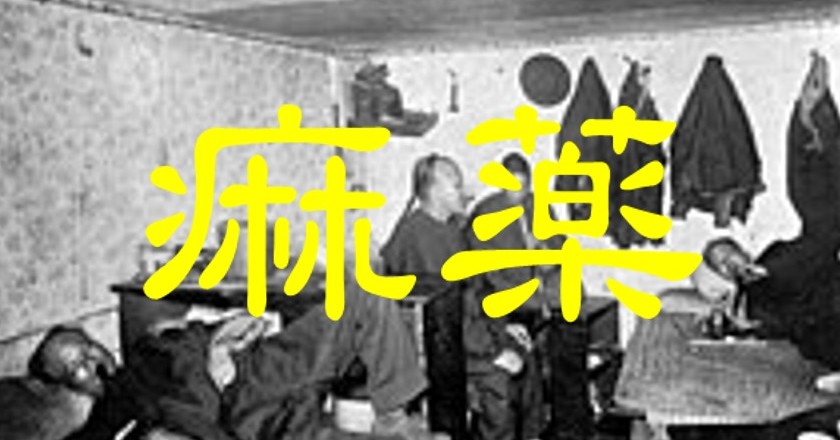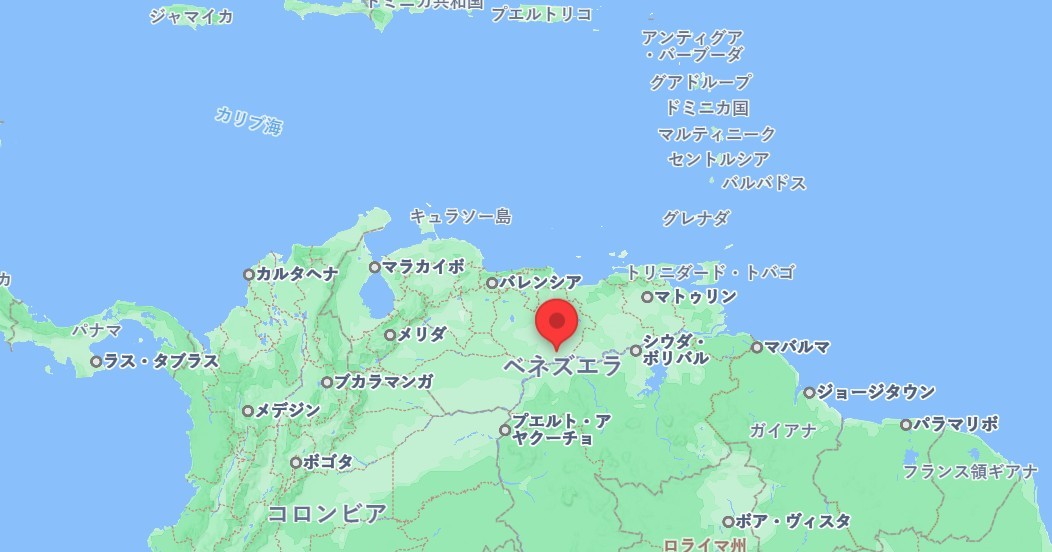薬物の犯罪化と非犯罪化を考える

ポルトガル、リスボンの街並み
はじめに
薬物政策はしばしば感情的な議論になりがちであり、そのため異なる意見をもつ人びとが互いの立場を正確に理解したうえで議論することが難しいといわれている。
そこでまず、基本的な言葉の意味から押さえておきたい。
• 薬物の犯罪化(criminalization)
医療用途を除いて、薬物そのものが禁制品とされ、製造や輸出入、売買など、特定の薬物に関連する行為を法律で犯罪として禁止し、違反者に対して刑事罰(自由刑や財産刑など)を科す政策をいう。薬物の自己使用やそのための所持も一般に犯罪とされている。これは、薬物使用そのものを刑事司法制度を通じて積極的に取り締まり、罰するというアプローチである。日本を含め、多くの国によって採用されている。
• 薬物の非犯罪化(decriminalization)
これは、薬物の無許可での供給を違法としながらも、個人が特定の薬物を使用したり、そのための少量の薬物所持に対しては処罰しないとする政策である。非犯罪化は、薬物の製造や販売を合法化するのとは異なり、薬物の個人使用に焦点を当てている。非犯罪化された場合でも、薬物使用者を治療システムに従わせるために(軽い)刑罰を維持するという考え方もあるが、これは「強制的な治療」をある種の刑罰とみなす立場からは非犯罪化と相容れないとされている。
なお、制裁として、たとえばわが国の道交法違反に対する反則金のような、前科のつかない行政罰を予定する場合は、とくに「非刑罰化」(depenalization)と呼ばれる。
非犯罪化をさらに進めたものが薬物の合法化(legalization)である。これは、薬物の製造、販売、使用などに国がライセンスを与えて限定的に許可し、政府による規制や課税の下で市場を管理する政策である。アルコールやタバコに対する政策と基本的に同じである。
薬物使用を犯罪化する理由
薬物使用を犯罪化する理由としては、いくつかの考えがある。
まず、「乱用」という言葉じたい、社会の支配的な規範(ルール)からの逸脱という意味をもっているため、「薬物乱用」という言い方じたいがすでにバイアスを帯びているが、薬物使用犯罪化論は、薬物の乱用が使用者自身、その家族、そして地域社会に害をもたらすという考えに基づいている。この考えは、とくに日本を含め、私益より公益を優先する傾向があるアジア諸国において強いのだが、その根底には薬物の使用は反道義的行為であるという道徳的あるいは宗教的な非難も犯罪化のひとつの根拠とされることがある。
薬物使用率を社会的に許容できる範囲に抑えるためには、国家による強制的な施策が必要だと考えられることも理由のひとつである。
さらに、薬物使用者が自分自身に害を及ぼすのを防ぐというパターナリズム(その人のために国家が介入するという考え方)や、青少年を薬物の害から守るという目的もあげられる。
政治的な文脈では、「薬物に厳しい」姿勢が選挙戦略として有利だと考える政治家もいる。
薬物使用を非犯罪化する理由
他方、薬物使用の非犯罪化を支持する理由もいくつかある。
最も基本的なものとしては、薬物の自己使用はリストカットやオーバードーズなどと同じ、いわば自傷行為であり、自殺が処罰されていない以上、合理的な理由がない限り、誰も罰せられるべきではないという考え方がある。
また、薬物非犯罪化論は、既存の薬物禁止法がもたらす様々な問題や害(使用者に対する烙印=スティグマ化、治療への妨げ、薬物使用者を使ったおとり捜査の乱用など)を減らすことができるという観点からも支持されている。
さらに現実の問題として、犯罪組織とのつながりを断つこと、薬物の品質を保証し安全性を高めること(これは合法化に近い議論だが、非犯罪化論にも関連する)、薬物使用に伴う非金銭的なコスト(逮捕の可能性や犯罪者との接触など)をなくすこと、そして「禁断の果実」効果(禁止されていることで逆に魅力が増し、欲望の対象となる)が減少する可能性なども非犯罪化のメリットとして挙げられている。
依存症を学習障害として捉えることで、害を減らすための政策がより効果的になるという考えもある。
問題点としては、「売人が売ることを禁じられているものを、消費者が買うのは許可する」というパラドックスである。たとえばわが国の刑法では、わいせつ図画を販売することは犯罪(刑法第175条)であるが、それを買うことは犯罪ではない。これは、わいせつ図画を広めることは社会の善良な性風俗を乱す行為であるが、それを個人がひそかに持つことじたいは社会の風紀を乱すものではなく、私的な自由の範疇に属する行為であると解されている。しかし、この理由が薬物使用非犯罪化論にも妥当するかどうかは、後の哲学的議論とも関係してくる。
なお、1920年代のアメリカ禁酒法(ボルステッド法、Volstead Act=National Prohibition Act)は、高価な大失敗だったと非難される傾向があるが、同法は、飲用目的でのアルコール飲料の醸造や販売、運搬、輸出入を禁止しており、使用(飲用)は禁止してはいなかった。これは、薬物非犯罪化政策と構造的にまったく同じなのである。アルコールと他の薬物とでは、何が異なるのだろうか。
薬物の合法化の問題点
薬物合法化論は、非合法市場に壊滅的打撃を与えるもっとも有効な方法は、違法薬物の供給から消費を合法とすることであるという。しかしその場合、消費と依存の大幅な増加が避けられないのではないかという懸念があるため一般に支持されていない。
しばしば合法化の例として挙げられるのがオランダの大麻政策である。
しかしこれは、完全に合法化を実現したものではない。オランダは、現在の世界的な薬物規制体制の枠組みを構築した麻薬に関する単一条約(1961年)およびオランダが加盟しているその他の国際的な薬物協定に則り、他国で違法とされている薬物の製造と販売を違法としている。ただし、1976年に大麻の限定数量(1回あたり)の販売について例外が設けられた。この行為は形式的には違法であるが、取締りの対象にはなっておらず、数百軒ある「コーヒーショップ」が少量の大麻を公然と販売している(ただし、1996年に30グラムから5グラムに引き下げられた)。しかし、大麻の栽培は依然として犯罪であり、輸入も同様である。コーヒーショップの表玄関はほぼ合法な商売だが、商品が入ってくる裏口は完全に違法であるとよく揶揄(やゆ)されている。オランダでは、生産と卸売りを違法とすることで大麻の価格を高く保ち、マーケティングを最小限に抑えている。オランダの大麻使用率は、コーヒーショップが普及し始めた1984年から1996年の間に、アメリカ、イギリス、カナダに比べればはるかに低いレベルではあったが、およそ2倍になった。西ヨーロッパの他の地域でも、同じ時期に有病率が上昇している。
薬物の流通が完全に合法化されれば、簡単に薬物が入手できるようになるだけでなく、価格も大幅に下がるだろう。しかし、そのことが全体としての薬物消費量を伸ばすだろう。合法化後の消費量はそれまでの数倍になるといわれている。ヘロインやコカイン、覚醒剤はすべて、大麻よりも入手が難しく、しかも高価であるため、最初の数年間の消費量の増加は、大麻よりもこれらの薬物の方が比例して大きくなる可能性がある。消費と依存が増加することは確かだろうが、しかしどの程度増加するかは誰にも予測できない。
世界の潮流はどうなっているのか―ポルトガルの実験―
少なくとも大麻に関しては、世界は明らかに薬物使用非犯罪化政策に向かっている。
たとえばウルグアイ(2013年)、カナダ(2018年)、タイ(2022年)、ルクセンブルク(2023年)、ドイツ(2024年)など、多くの国や地域で嗜好用大麻の合法化や非犯罪化が進んでおり、アメリカでも連邦レベルでの合法化の動きが見られる。国連麻薬委員会も大麻の医療効果を認め規制を緩和しており(2020年)、さまざまな国際機関が厳しい処罰を避けるよう勧めている。世界の潮流は明らかに大麻の自己使用や所持の非犯罪化(刑罰の回避)へと向かっている。
このような動きの先駆けとなったのがポルトガルである。
ポルトガルでは、1980年代から90年代にかけて違法薬物、特にヘロインによる被害が深刻になった。薬物使用率は、ヨーロッパの他の国に比べて全体的に低かったが、ヘロイン使用者のほとんどが深刻な依存症に陥り、HIVや肝炎の罹患率も高かった。20世紀末には、薬物問題は国家喫緊の課題となった。
このような中で、1999年、ポルトガル議会は新しい国家戦略(2001年発効)を承認し、薬物自己使用を原則として刑事司法の対象から外した。平均10日分未満の薬物(大麻5グラム、ヘロイン1グラム)を所持している者はそれを警察に没収され、72時間以内に「懲戒委員会」(dissuasion board)に出頭しなければならない。この委員会は通常、精神科医と法律家で構成され、薬物使用者を、娯楽的使用者、常用者、依存症患者に分類し、リスクを警告し、適切であれば治療を提案する。 罰金から社会保障給付のカット、リハビリ施設への強制的通所など、さまざまな制裁がある。10日分以上の薬物を所持して摘発された場合、ドラッグ・コート(薬物裁判所)で裁判を受けなければならず、刑務所に収監される可能性がある。
原則として刑事司法のレールに乗せられるおそれがなくなったことから、自己申告の結果、治療を受けるヘロイン依存症患者の数は増加した。新規HIV感染者も15~19歳の薬物使用者も減少している。新制度により、闇組織は年間最大で4億ユーロ(数百億円)を失ったといわれている。
一部の保守的な政治家は、非犯罪化が薬物使用の大幅な増加につながり、ポルトガルが「薬物ツーリズム」の対象になるのではないかと懸念していたが、そのようなことは起こらなかった。
ポルトガルにおけるもっとも大きな変化は、薬物依存症に対する社会の態度である。今では、薬物依存は道徳的・犯罪的な問題ではなく、医学的・社会的な問題としてとらえられている。
ポルトガルは「薬物に甘い」どころか、これまで以上に国が積極的に介入し、嗜好品としての使用から依存症になることを抑止する措置を講じ、治療への参加を手厚く奨励している。その結果、ポルトガルでは治療と社会復帰が増加し、同時に薬物の過剰摂取による死亡、HIV感染、収監率、ホームレス、違法薬物使用も減少した。2023年版世界平和指数によると、ポルトガルは現在、世界でもっとも安全な国のひとつとなっている。これが一般的な評価である。
薬物政策と哲学的な議論
薬物政策の議論で、ジョン・スチュアート・ミルの有名な「加害原理」に言及されることがある。これは、文明社会のあらゆる構成員に対して、その意思に反して権力を正当に行使できる唯一の目的は、他者への危害を防止することであるというものである。本人の利益のため、本人の幸福のため、あるいはそうすることが賢明だからという理由で本人に強制や禁止を課すことは正当化できないという。
しかし、加害原理は「文明社会の全員」が誘惑に負けないという条件で成り立つものであり、現実には私たちの多くが内省すればこの主張が誤りだとわかる。現実には、常に自分の思うように行動している人はほとんどいない。
薬物使用の扱いが難しい政策問題であるのは、薬物摂取が他の行為よりも合理的に自己統制しにくいからである。つまり、国家が人びとをかれら自身から守ることは、単純に良いことのように思えるからである。
薬物を使用したいと望む多くの人が、依存症になりたいと望むわけではない。ミル自身が述べていることだが、安全でない橋を渡ろうとしている人を、危険を警告するいとまがない場合に拘束して引き返させることは、その人が川に落ちることを望んでいない以上、自由を実質的に侵害するものではない。つまり、本人が望まない危険(依存症など)から守るために、国家が介入することは自由の侵害ではないということである。しかし「加害原理」は、どの程度の薬物規制で十分かという現実的な事実の問題には答えられない。これを考える手がかりとなるのは、「比例原理」である。
「比例原理」とは、処罰するにしてもおよそ刑罰はその行為から生じる害悪と釣り合っていなければならないという考え方である。ジミー・カーター元アメリカ合衆国大統領の次の言葉ほど、比例原理を的確に表現したものはない。
「薬物の所持に対する罰則は、薬物の使用そのものよりも個人を傷つけるものであってはならない」(1977年の議会メッセージ)。
当時は、クイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」が全米のチャートを席巻していた頃である。薬物の身体的な害悪は、薬物の種類によってもさまざまであり、それに応じた柔軟な政策が必要なのである。
薬物政策の議論には、「薬物とは何か」、「依存症とは何か」(病気か罪か)といった原理的な問いが深く関わっている。食品、薬物、毒物は明確なカテゴリーを持たず、嗜好用と医療用の区別も曖昧である。アルコールやタバコも薬理的には薬物である。依存症を「罪」と呼ぶべきか、「病気」と呼ぶべきか、あるいは「犯罪」と呼ぶべきかは、社会が依存症患者にどのように対応すべきか(怒りか同情か、罰か援助か)という見方をも反映しているのである。
結論
「薬物の犯罪化」は、薬物の自己使用そのものを犯罪とし、刑罰を科すことで薬物による害や犯罪を抑制しようとするアプローチであるが、これは非合法市場の活性化、暴力犯罪、スティグマ化などの問題を抱えている。
これに対して「薬物の非犯罪化」は、個人使用に対する刑事罰をなくして、公衆衛生やハームリダクションの観点から薬物使用に対応しようとするアプローチである。薬物使用に関する教育の改善、向上、特に依存症の本質や原因に焦点を当てること、多様な治療選択肢(専門家による治療、自助グループなど)を提供することも重要である。また、薬物以外の方法で意識を変容させる方法を学ぶこと、薬物の規制方法と対象(課税、年齢制限など)も重要な政策問題である。
ただそのような政策の充実のためには、何よりも薬物自己使用の非犯罪化がデフォルトの立場でないといけない。そして、薬物の有害性の程度に応じて、その後の柔軟な対応を検討すべきである。
薬物政策は、法制度や科学的根拠だけでなく、個人の自由、自己決定、パターナリズムといった哲学的な議論や、文化、歴史、社会的な価値観によっても影響を受ける多角的な課題である。現実的な問題解決には、抽象的な原理だけでなく事実に基づいた議論が必要であり、ハームリダクションや教育、治療といった包括的なアプローチが不可欠なのである。(了)
すでに登録済みの方は こちら