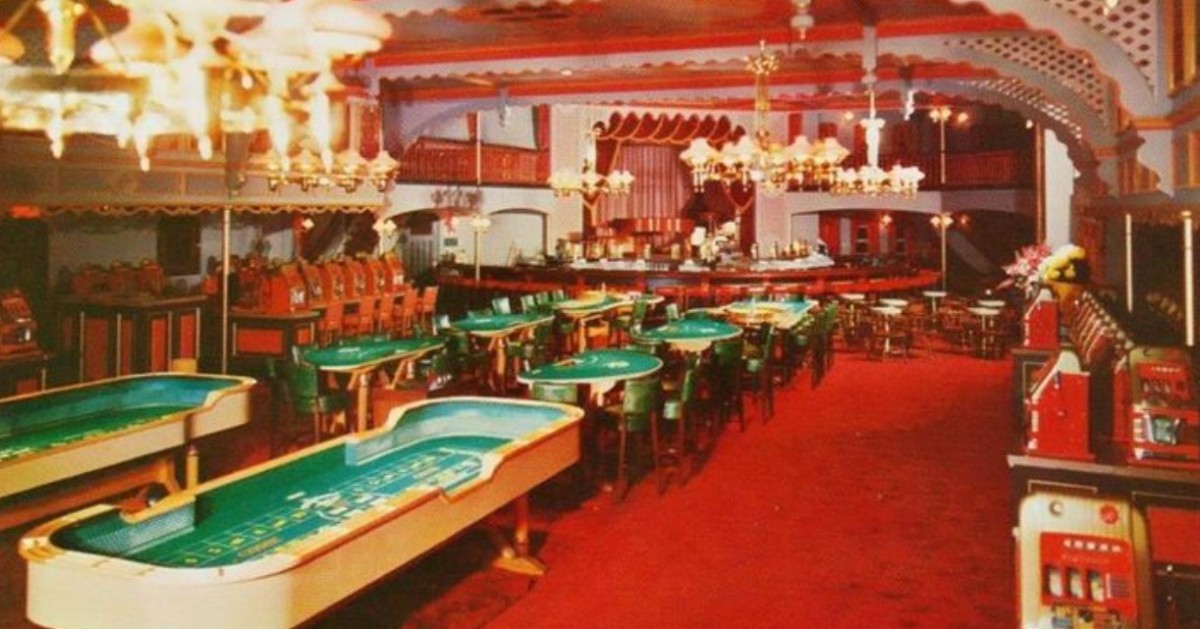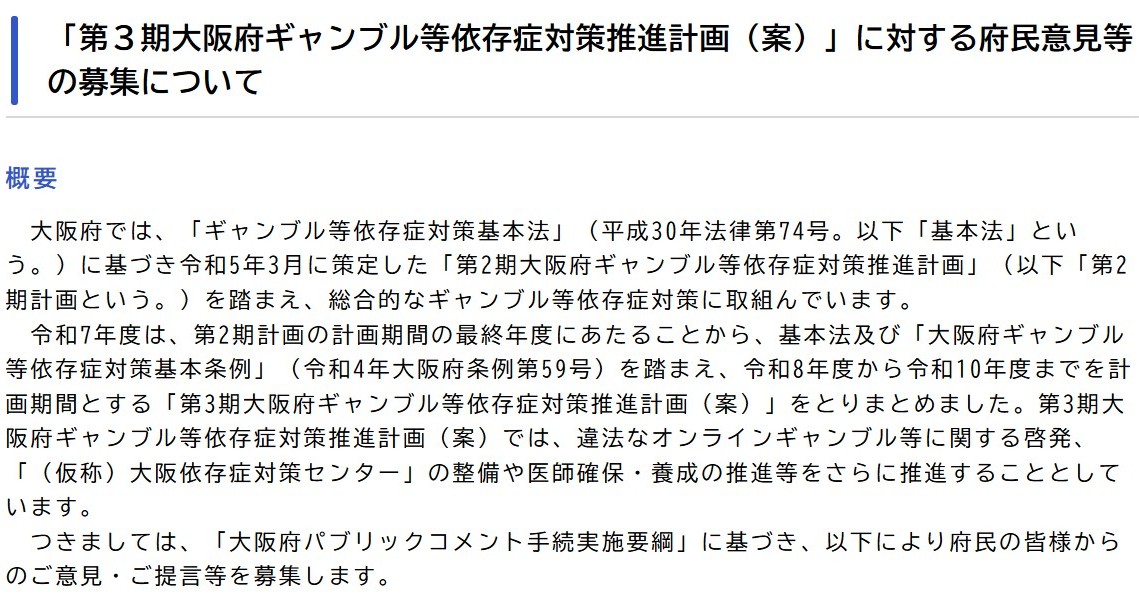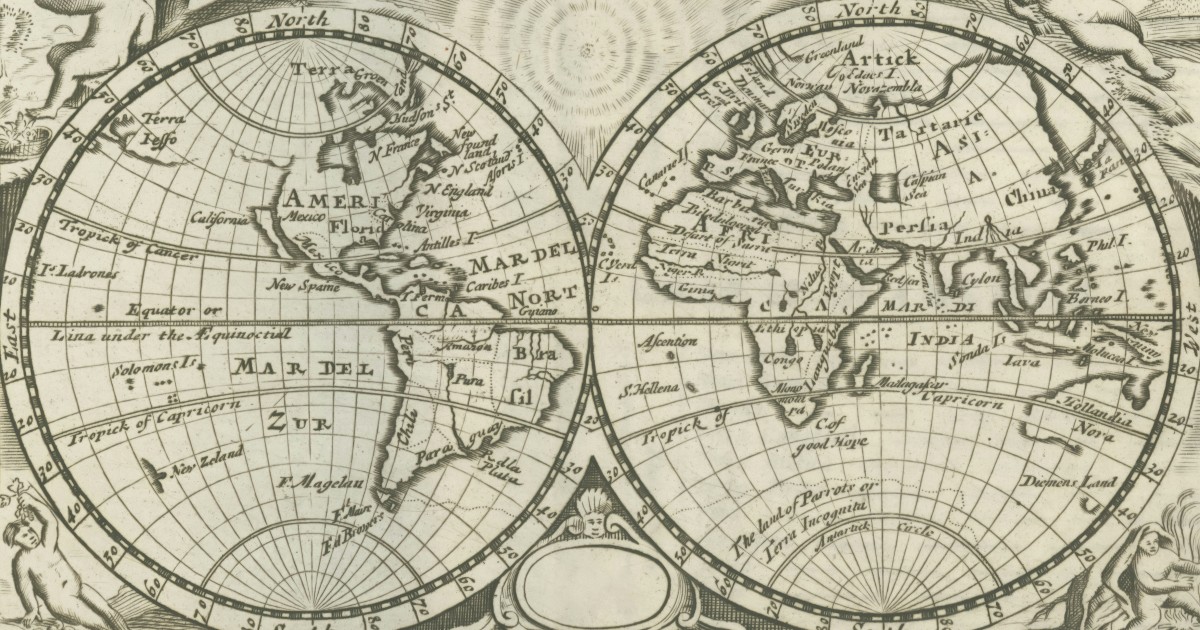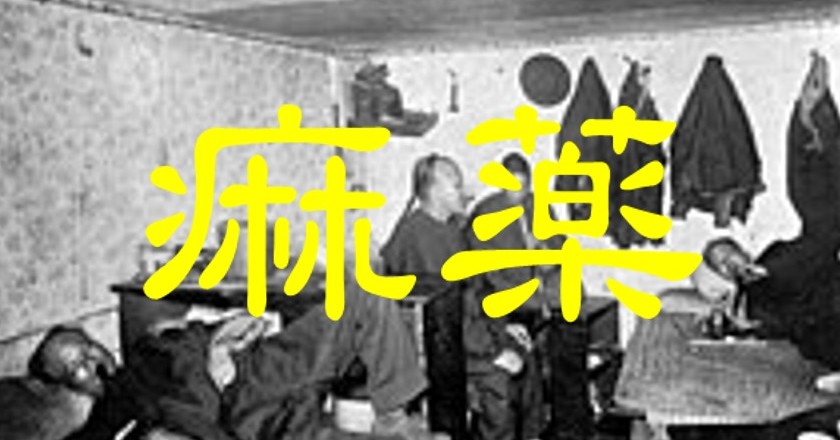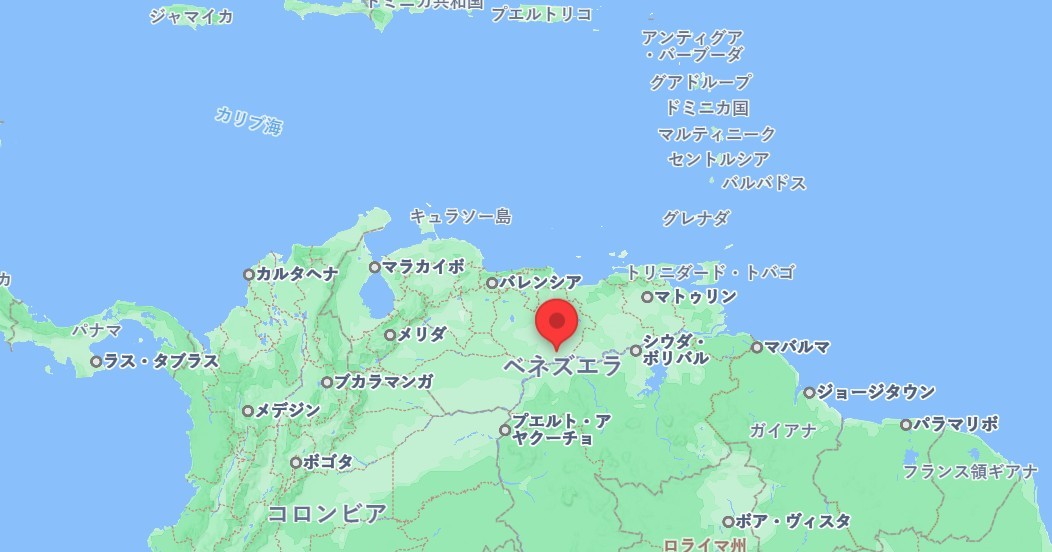法的パターナリズムと薬物政策

1.はじめに
法的パターナリズム(Legal Paternalism)とは、国家が個人の自由な自己決定や自律性、志向、好みまでをも制限して、個人の健康や財産などをその個人のためを思って保護することを正当化する規範的な論理である。一言でいえば、国家のお節介である。この概念はとくに薬物政策において、(未成年はともかく)成人の娯楽目的の薬物使用を禁止し、使用者を処罰する政策の暗黙の根拠として機能してきている。その核心には、「個人が被るかもしれない危害からその個人を守る必要性が、その個人の権利や自律性の行使の保護を上回ることがあるのか」という、自由と権力の境界に関する哲学的で規範的な問いが存在する。
2.法的パターナリズムの論拠とその歴史的背景
薬物政策におけるパターナリズムの論拠は、主に個人の健康と福祉の保護に向けられている。薬物の非犯罪化が提案されると、その薬物は使用者の健康に害を及ぼすというはなしが必ず持ち出される。確かに国民の健康の維持は国家の最も重要な責務であり機能の一つであるが、問題はそれが懲罰的介入の正当な理由になると信じられていることである。薬物使用が犯罪化され、使用者が「犯罪者」とされるのである。
薬物依存が進行すると、薬物使用者はまるで「ゾンビ」(生ける屍)のように描かれるなど、依存症の恐怖を著しく誇張するレトリックが、政府やマスコミによって広められてきた(「ダメ。ゼッタイ。」キャンペーンなど)。このような極端なイメージが、懲罰的な介入の必要性、正当性を国民に訴える上で、きわめて効果的に利用されてきた。
またパターナリズムは、道徳的で高潔な行動や公衆道徳の維持を求める反悪徳運動にも根ざしており、モラリスティックなキャンペーンは、酩酊物質の使用を、都市的な堕落に身を委ねる不健全な習慣とみなし、個人の自律と道徳的な健全性を強調する伝統的な価値観と対立させてきたのである。
3.個人の自律性と犯罪性
(1) 自己損害と他害の区別
薬物使用は、本質的に他者に危害を加える犯罪(殺人や傷害、強窃盗、レイプなど)とは異なる。これらの犯罪を処罰する根底には、「目には目を、歯には歯を」という意味での応報原理という道義的な正当化原理が存在するが、薬物の自己使用についてはそのようなものは存在しない。
つまり、他害行為は、必ず特定の被害者の権利(生命や身体、財産など)を侵害するが、多くの娯楽用薬物使用者は、薬物の使用じたいで誰かの権利を具体的に侵害することはない。薬物使用が他者に有害であるとされるのは、その行為そのものの他害性ではなく、危害のリスクや可能性を許容できないほど高めるという、一段階距離のある間接的な理由によるものなのである。
基本的に「自分にしか害を及ぼさない」行為に対して、すべての薬物使用を危険だとして、その使用者を罰することは飛躍した考えである。強力な抗がん剤が正常な細胞も破壊するように、処罰という国家の行為は、その対象や要件が細かいほど望ましいのであり、大きな要件設定は好ましくない弊害を招く。例えば薬物を摂取した状態での自動車運転や危険な作業など、個々具体的に評価して、個別に犯罪化すべきなのである。
(2) 依存症と自律性の問題
パターナリスティックな介入の正当性は、依存症が個人の自律性を完全に奪うということを前提としている。薬物依存者は、薬物使用に対して効果的に抗うことができず、使用を止める力がないという点で、自律性を損なっているとされる。
しかし、薬物常用者の大半は依存にはならないといわれている。これは、常用的に飲酒を続けている者の大半がアルコール依存症になっていないという、われわれの経験から判断しても納得できることである。依存は常に相対的な現象であって、常用者であっても決して「薬物の奴隷」ではない。常用者であっても、薬物使用が自律的で自由であることを否定する理由はない。
4.政策の不均衡性と道徳的根拠の欠如
(1) 合法的な悪習との不均衡
タバコやアルコールは、社会に甚大な害(タバコは世界で年間約800万人の人生を縮め、アルコールは約300万人の死亡原因となっている)を強いているにもかかわらず、多くの国や地域で合法であり、使用を禁止して罰すべきだという議論はほとんどされない。アルコールは乱用可能な薬物であることは疑いようがないが、税収や「社会の潤滑油」としての効能など、その使用は逆にさまざまな利益ももたらすと考えられている。
さらに、処方薬や市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)が深刻な社会問題となっているにもかかわらず、風邪薬や咳止め薬を一気飲みして救急搬送された者を罰すべきだという意見は見たことがない。違法薬物の禁止とこのような他の自己損害行為との間には座視できない不均衡が存在する。
(2) 道徳的な区別の欠如
なぜ違法薬物の娯楽的使用は不道徳であると考えられているのか。この問いは、現代の薬物政策における最大の対立軸の一つである。殺人や強盗が不道徳であることは、他者の権利侵害という議論の余地のない理由によって肯定される。しかし、娯楽目的の薬物使用者がただちに誰かの権利を害したり侵害したりすることはないため、禁止論者は、違法薬物の使用をなぜ道徳的に非難すべきかの根拠を提示できないことが多い。
このため、道徳的に許される薬物(アルコール、タバコなど)と、道徳的に禁止されるべき薬物との間に、関連する違いがあるのかという根本的な疑問が提起される。この違いが提示されない限り、違法薬物に対する道徳的な反論は、道徳的な議論に見せかけた根拠のない偏見である。
5.懲罰的パターナリズムがもたらす逆効果
(1) 刑罰によるスティグマと社会的排除
法的パターナリズムに基づく政策は、個人の保護という目的とは裏腹に、より深刻な危害を引き起こすという逆説的な結果を生み出している。
薬物使用を犯罪化することは、故意にスティグマを作り出すことである。ある行動を犯罪化し、同時にスティグマをなくすことは不可能である。
スティグマは、薬物問題を持つ人びとが問題を認めたり、治療を求めたりすることを妨げ、公衆衛生の目標(回復と社会復帰の促進)を損なう。逮捕され処罰されるという行為は、薬物が青少年に与える可能性のある害よりも明らかに有害であり、個人の生活展望を破壊し、家族の崩壊や社会復帰の困難を引き起こす。薬物使用者は「道徳心の欠落した堕落した人間であるかのように感じさせられ」ることで、残された尊厳の感覚を奪われる。
(2) 組織犯罪の強化と暴力の増大
禁止法は、薬物市場の管理を犯罪組織に委ねる結果をもたらし、彼らは薬物のサプライチェーン全体をコントロールする。違法薬物市場は、絶対的禁止法の下で絶対的な独占状態となり、異常な利幅を提供する。
この違法なシステムでは、使用者と売人の関係が法の外で行われるため、紛争は裁判所では解決できず、非常に「乱暴な正義」が常態化する。薬物市場から生じる暴力犯罪の圧倒的な証拠は、禁止法によって生み出された市場からもたらされている。
(3) 政策の失敗とエスカレーション
薬物使用を犯罪化するアプローチは、社会における薬物使用のレベルに影響を与えず、根本的な解決にはなりえない。にもかかわらず、薬物法は「社会のニーズに適応できないことが無視され、むしろ、さらなる抑圧によってさらなる熱意をもって施行されるため、反抗の連鎖を助長しながら、より多くの害をもたらす」という失敗とエスカレーションのサイクルが続いている。
また、薬物使用者を刑務所に入れる代わりに治療を受けさせるという提案も、特定の薬物犯罪および窃盗罪に対する刑罰を重くするカリフォルニア州の「提案36」のように、治療を受けなかったりうまくいかなかったりすれば投獄されるという点で、強制的な治療を刑罰の一種とみなすものであり、非犯罪化とは相容れない。非犯罪化とは、国家が薬物使用者を治療させることさえも、投獄することと同じように許されないと考える立場である。
6.最後に―公衆衛生パラダイムへの転換
非犯罪化は、合理的な解決策が存在しない場合に、政策が選択すべきデフォルトのポジションである。非犯罪化の最大の受益者は、懲罰的制裁に苦しんでいる人びとである。非犯罪化によって、薬物使用者は逮捕や起訴を恐れる必要がなくなり、生活が改善される。また、非犯罪化は薬物の供給の非犯罪化とイコールではなく、合法化によって薬物は国家による規制の対象となり、効果的な管理が可能となる。
薬物政策の焦点は、公衆衛生上の視点を優先して、薬物に関連する健康被害(依存症、過剰摂取、感染症の伝播など)の削減である。薬物政策を保健政策の一部に組み込み、供給規制の第一次的な目標を、すべての薬物使用の抑制ではなく、健康を促進し、健康被害を最小限に抑えることに設定するべきである。
薬物使用を刑事司法の問題から外せば、薬物はアルコールの場合と同じように医療的・社会的問題になるだろう。この転換は、国民の生命、健康、尊厳を守るという国家の任務に沿う唯一の責任ある答えであり、そのような観点から市場を規制・管理し、薬物の科学的な危険性に応じた規制を確立し、監視・実施することが可能となるだろう。(了)
すでに登録済みの方は こちら