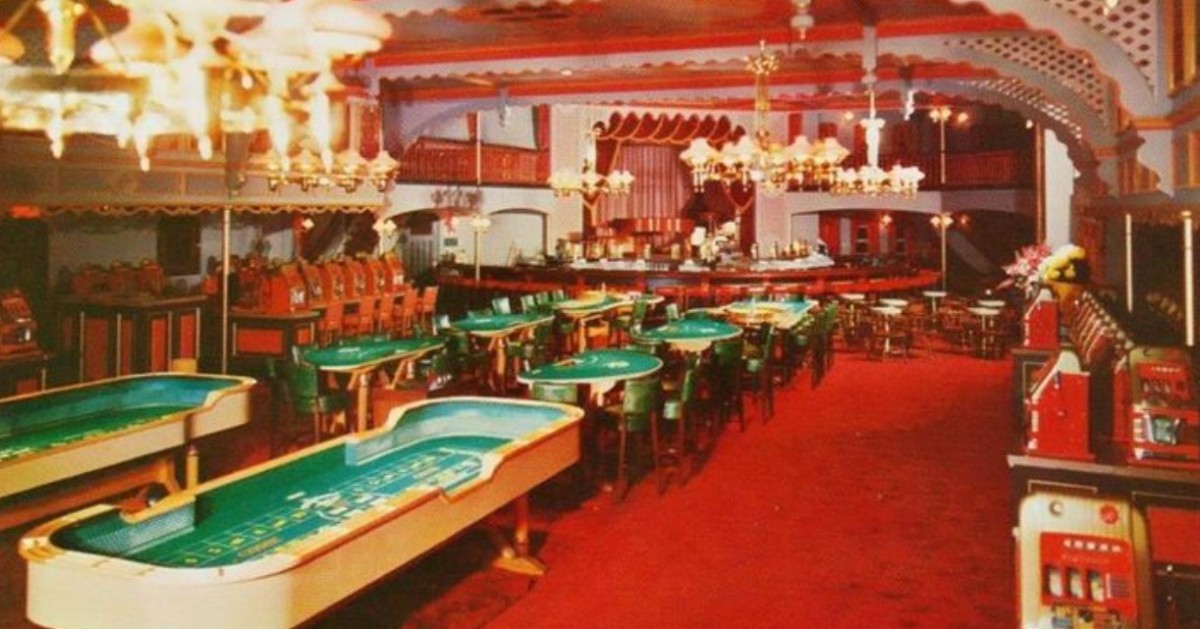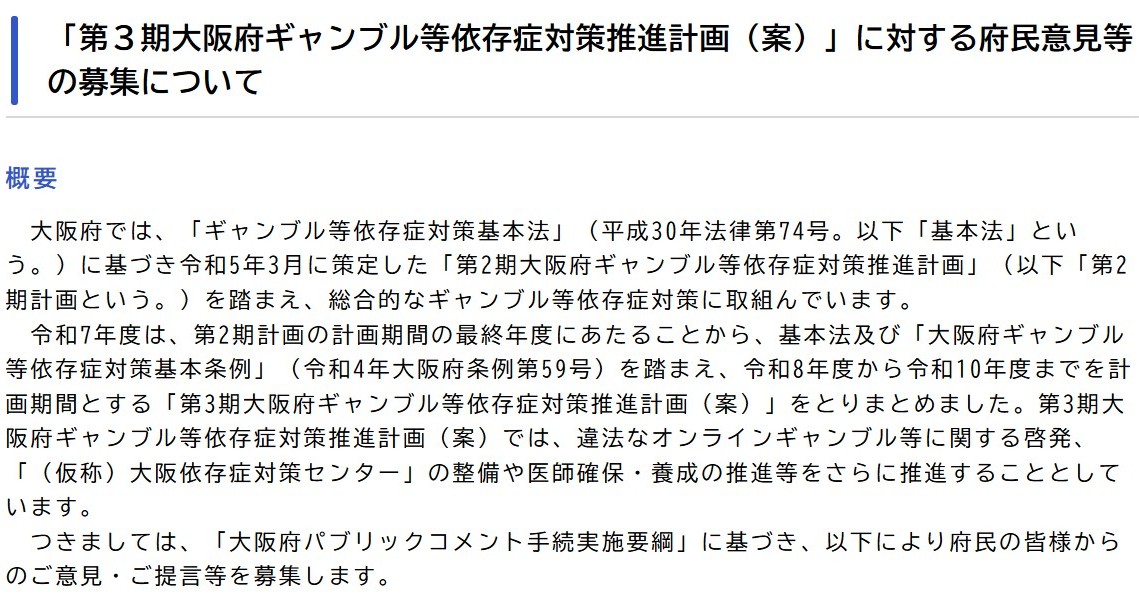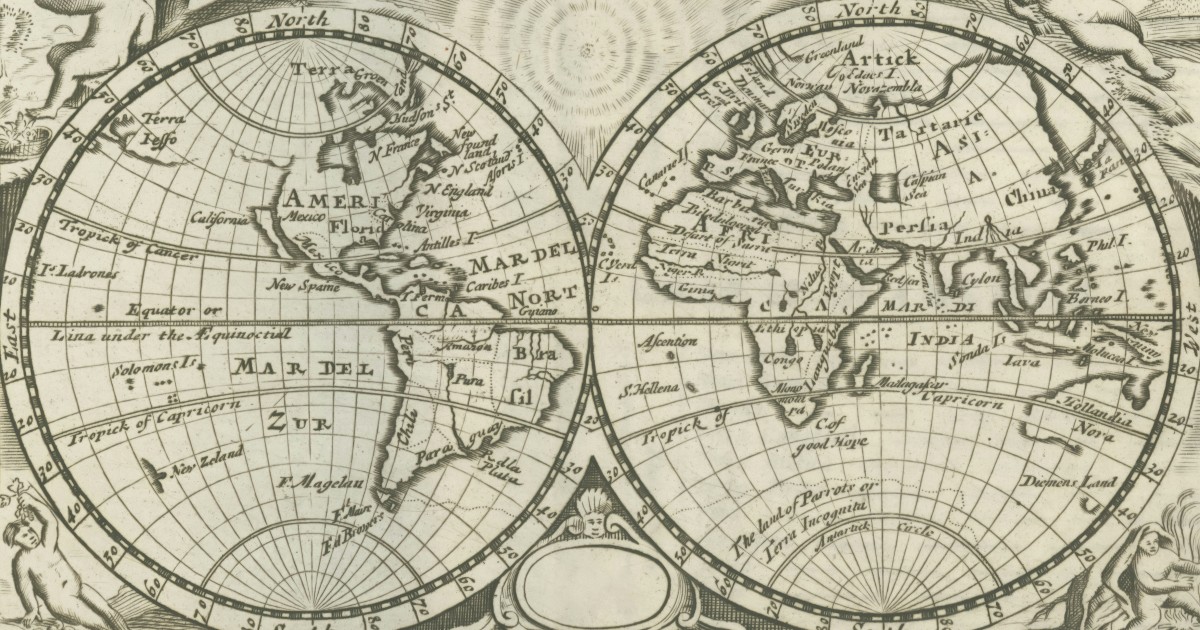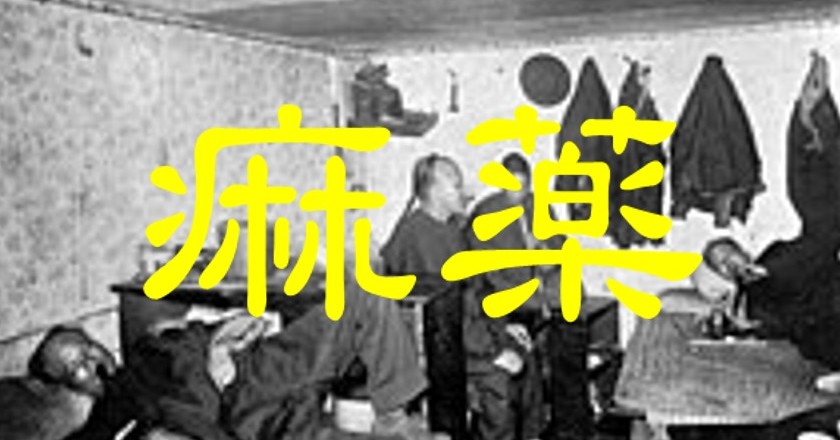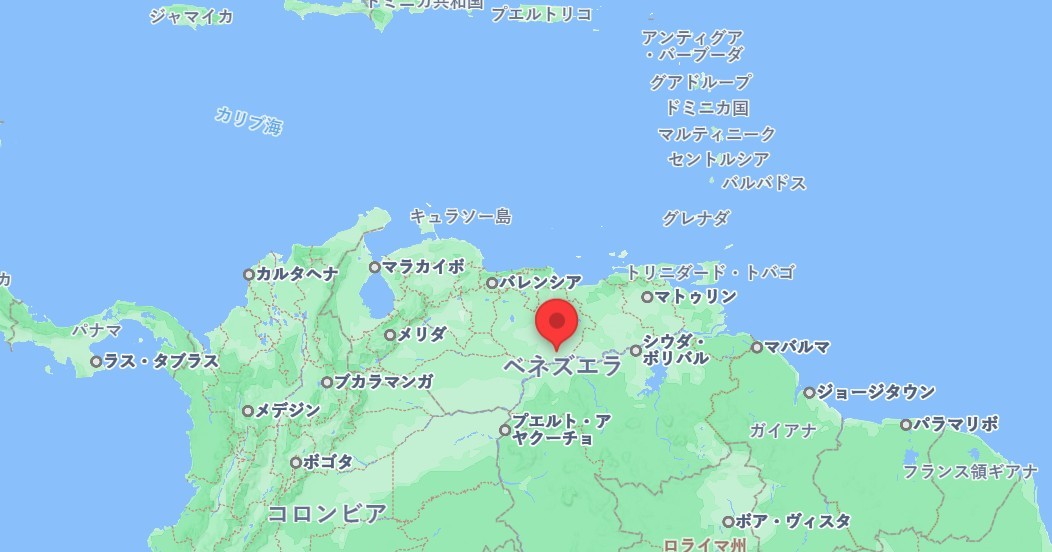不快だという理由は、その行為を犯罪化するための十分な根拠となり得るか

1.はじめに
ある行為が「不快だ」という理由が、それ単独でその行為を犯罪化するための十分な根拠となり得るかという問いに対し、現代の刑法理論は原則としてこれを否定するのである。刑罰は国家権力の行使における最も厳格で重大な制裁であり、その適用には極めて慎重な判断が求められるからである。
2.刑法の基本原理と道徳の限界
法益保護の原則の確立
刑法が何のために存在し、どのような行為を犯罪と定めるかという根本的な問題において、現在の通説的な見解は、「法益保護の原則」に立っている。
すなわち、刑法は、道徳や倫理といった抽象的な価値観の維持を目的とするのではなく、個人、社会、国家にとって保持されることが必要かつ適切であると認められる一定の具体的な利益、例えば、個人的利益でいえば、生命や身体、財産など、あるいは社会的利益でいえば、通貨や文書の信用性など、また国家的利益でいえば、日本国の憲法秩序や公務の執行、良好な国交の維持など、そのような具体的な利益を刑罰を背景に保護するのである。これらは「法益」と呼ばれ、言葉を変えると、刑法という法律は法益を保護するために存在すると理解するのである。
したがって、ある行為が刑法によって処罰されるべき根拠は、その行為が「道徳的に悪い行為」「他人にとって不快」であるからではなく、刑罰権を発動しなければ収まらないほど「重要な法益を侵害し、または侵害する危険を生じさせる行為」であるから、とされる。道徳や倫理に反するという理由だけで刑罰を科すことは、このような意味における「侵害原理」に反するとされるのである。
3. 価値観の多元性の尊重
3-1 政治的な濫用や高まった感情だけによる処罰
公共の福祉、道徳、倫理といった概念は、人によって、また時代や場所によって考え方が異なり、歴史的にも変化する流動的・相対的なものである。日本国憲法が想定する社会は、価値観の多元性を許容する個人主義の社会であり、他人に具体的な迷惑をかけない限り、多数派と異なる行動基準に従うことも認められるべきである。
もし刑法が特定の道徳や倫理を強制する役割を担うならば、それは国家が個人に対し、国家が望む通りの生き方を強制することになりかねず、国民の自由を不当に侵害し、ひいては法的安定性を損なうことになる。刑罰の根拠として道徳や倫理を用いることは、その概念が曖昧で無限定であるため、政治的な濫用や高まった感情だけによる処罰を引き起こす危険性も指摘されている。
3-2 「公共の福祉に反する」という概念の実質
しかしながら、判例や学説の中には、賭博罪やわいせつ罪といった特定の犯罪類型(風俗犯)の処罰根拠を説明する際に、「公共の福祉に反する」といった文言が用いられる例は存在する。しかしその発想の当否は別として、この立場ですら、その実質は抽象的な道徳観念の維持に留まらず、それを具体的な社会的有害性、すなわち社会法益の侵害または危険の防止に還元して捉えているのである。
例えば賭博行為は、一見すると自己の財産を自己の好むところに投ずる自由な行為に属するように見えるが、判例・通説は、その本質が公共的犯罪であると捉えている。処罰の根拠は、単なる道徳違反ではなく、「国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風を害する」ばかりでなく、暴行・脅迫・強窃盗といった「副次的犯罪を誘発し、又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらある」という社会的有害性にあるとする。
したがって、賭博罪の禁止は、射幸心を過度に煽り、詐欺的な運営が生じたり、暴力団の資金源となるなどの「より大なる悪を避ける」ための法政策的手段であり、健全な経済的風俗(社会生活環境)を保護する社会的法益に対する罪としてその合理性が説明されているのである(なお、私見はこれとは異なるが、ここで述べることは控える)。
公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等罪についても同様である、
善良な性風俗という抽象性の高い観念を理由に処罰することは正当化されないが、通説は、これらの規定を「社会の健全な精神的・文化的環境」という法益を保護するためのものとして理解している。つまり、この「健全な精神的・文化的環境」が害されることによって、性的表現に触れたくない人々の権利が脅かされたり(見たくない者の自由)、青少年に有害な環境が形成されたり、商業主義的傾向が濫用されたり、暴力団の資金源になるなどの弊害が生じるおそれがある。これらの弊害の防止は、抽象的な道徳ではなく、実質的な社会の利益(法益)の保護を目的としていると解釈されているのである。
4.結論
行為が「不快だ」という評価は、たしかに刑法が介入する一つの契機となり得るものの、それ自体が刑罰を科すための独立した根拠となるわけではない。処罰が正当化されるためには、当該行為が「法益の侵害またはその危険」という実質的要件を満たし、さらに刑罰以外の手段では十分に法益を保護できない場合に限って、補充的に適用されるべきなのである。これは、刑法の「謙抑性の原則」と呼ばれている。
つまり、刑法は道徳規範そのもの維持を目的とするのではなく、国民の自由や権利を保障しつつ、社会の存立と個人の生活基盤を脅かす実質的な法益侵害・危険を伴う行為に対してのみ、法益保護の最終手段(ultima ratio)として適用されるべきであるといわれているのである。(了)
-
(追記)
なお、上で述べたことは、薬物の自己使用についても基本的に当てはまることである。
すでに登録済みの方は こちら