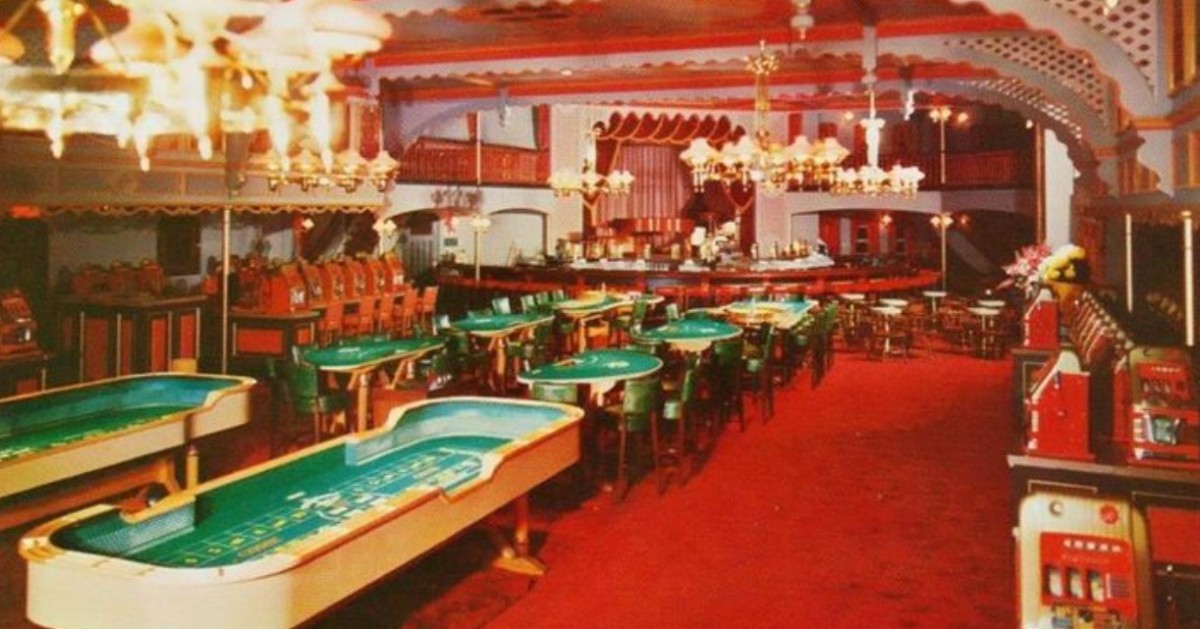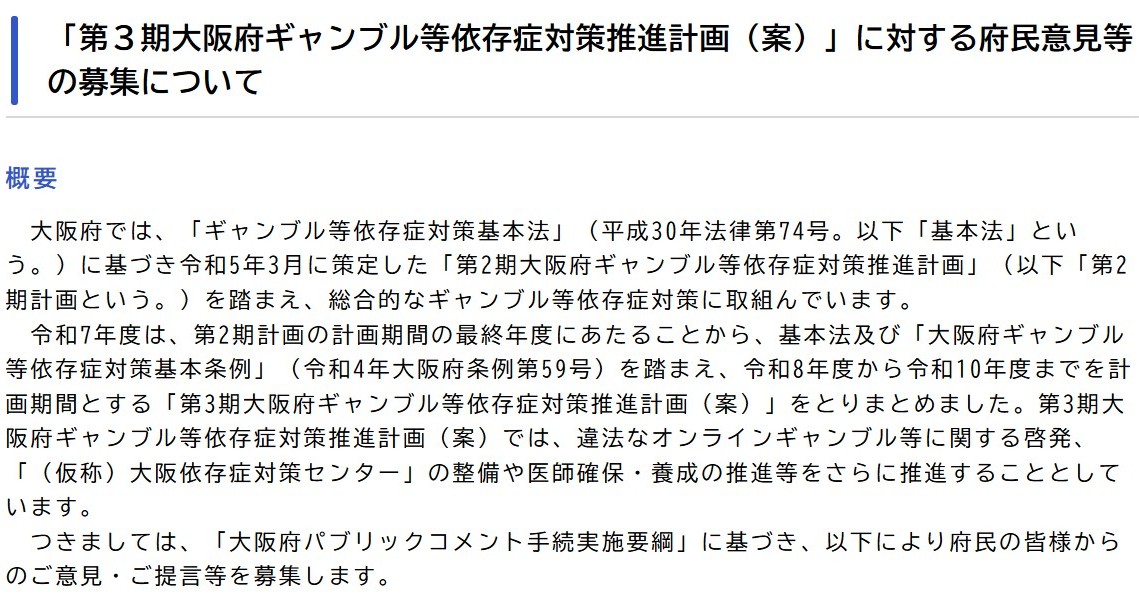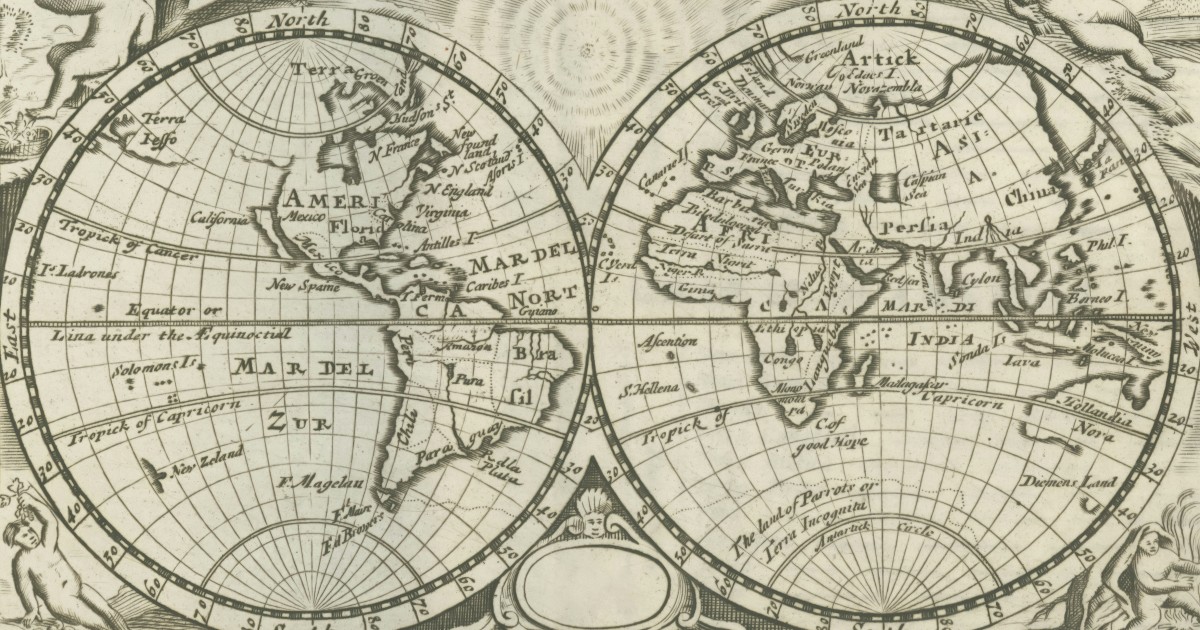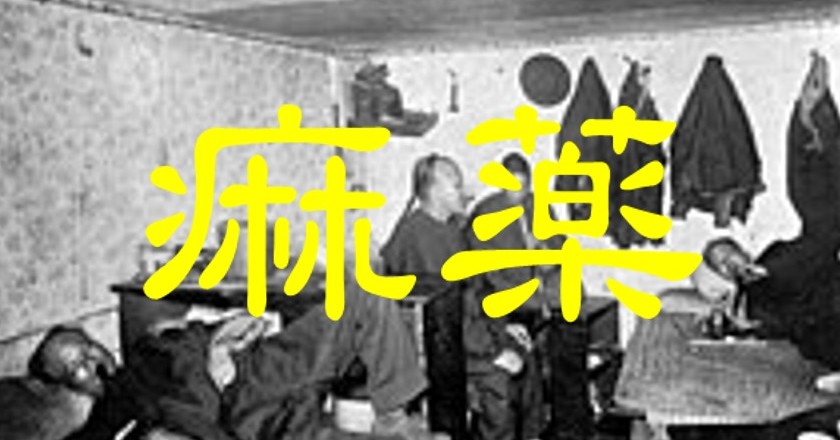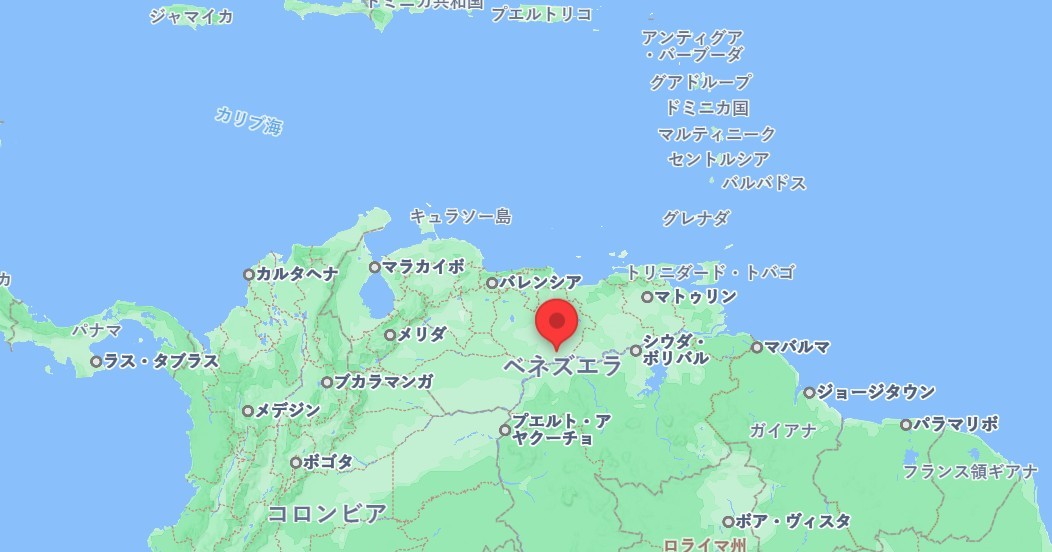薬物のはなしになると、ひとはなぜ感情的になるのか

by Myriam Zilles
1. はじめに
薬物の話題になると、議論はしばしば理性的なやりとりを超え、感情的な対立を引き起こす。「薬物」という言葉に、人びとは理屈ではなく、嫌悪、恐怖、あるいは道徳的な正義感といった感情で反応する。それは、薬物の問題が法律や公衆衛生の領域を超え、その深いところで人間の根源的な価値観である善悪や自由と責任、そして国家の役割といった大きな価値観の問題に刺さっているからである。
本稿では、このような感情的興奮がどのような構造のもとで生じるのかを整理する。そして、それが今の日本で強く支持されている懲罰的パラダイム(刑罰によって違法薬物をコントロールするという考え)をどのように支えているのかを考察して、その問題点を明らかにしたい。
2. 道徳とタブー
人びとが薬物について嫌悪や恐怖を抱く背景には、もともと人間には世界を「善と悪」に分類したいという根源的な欲求があるように思う。
薬物は「悪」の象徴として社会的に構築され、その摂取は道徳的堕落とみなされてきた。薬物問題は宗教的信念との親和性も高く、薬物使用は罪や自制心の欠如として語られ、「懲らしめ」による「浄化」の対象とされてきた。このような道徳的な信念は、単純な快楽そのものへの否定と結びついており、「陶酔や恍惚」といった感情は理性を惑わす危険で不健全なものであり、理性と勤勉を重んじる倫理観とは相容れないと考えられてきた。
この「快楽の否定」は、薬物使用への冷静な理解を阻み、政策においても「楽しいことのために薬を使う」行為を否定する考えと結びついている。薬物使用は道徳的堕落とみなされ、理性的な対話よりも感情的な反応や断罪を呼び込む構造が出来上がるのである。
3. 政治的プロパガンダと懲罰的パラダイム
薬物はまた、政治にとっても都合の良い象徴である。薬物犯罪はいわば大衆受けする政治的テーマであり、薬物乱用を非難すれば支持を得られるが、逆に薬物使用を擁護すれば攻撃される。あえていえば、社会問題の複雑な原因を単純化し、薬物というスケープゴートに投影することで、政治家は秩序回復の演出を行う。それは、薬物使用者を罰することで、社会にある種のカタルシスがもたらされるからである。「悪」を罰することで共同体の純潔が保たれるという応報思想のこの根本は、宗教儀礼にも似た効果を持っている。
こうして形成されるのが、懲罰的パラダイムである。この枠組みでは、「どのようにすれば薬物使用(乱用)を完全に止めることができるか」が重要な政策目標となり、代替的視点―ハームリダクション(根絶ではなく害を削減する政策)や社会的共存・包摂―は「薬物問題に甘い」として排除される。
さらに、薬物戦争は象徴的な「正義の戦争」としても機能する。そこでは逸脱者を排除することで社会の純粋性を回復するという幻想が述べられる。つまり、科学的なエビデンスに基づく政策評価よりも、逸脱者を厳罰に処して矯正するという道徳的満足が優先されるのである。それがいかに効果がないとしても、より強硬な手段に訴えることで正当性を保とうとする傾向を生むのである。
懲罰的パラダイムを維持する限り、薬物問題は終わらない。それは「悪と戦う」という物語を終わらせたくないという社会の無意識の願望であり、理性的な改革を妨げる最大の要因だと思われる。
4. 個人の自由と国家の介入
薬物問題が感情的になる第三の理由は、国家が個人の自律をどこまで認めるのかという、その境界線が問われるからである。
刑罰の正当化原理である「危害原則」は、道義的な応報原理(「目には目を歯には歯を」)を前提に、他者に損害を与えた者を罰することは正しいとする。しかし、薬物使用は基本的に自己にしか影響を及ぼさない行為である。このため、薬物の自己使用を罰する場合、国家が個人の身体や意識の領域に介入することが正当なのかという法哲学的な問題が生じるのである。
薬物使用者を刑罰によってコントロールすることは、国家が個人の精神や身体を統制するという強力なメッセージである。その行為を正当化するためには厳格な説明責任が求められるべきだが、実際には「本人のため」や「社会秩序のため」といった曖昧な論理で問題が正当化されている。しかし、こうした法的パターナリズム(父権的干渉)は、成人の自由な選択を保護するというリベラルな理念と鋭く衝突する。
また、依存症という特殊な状態は、この自律の概念を複雑にしている。薬物依存者は、薬物を後悔しながらも、強迫的に使用し続ける。この選択がはたして自由意志によるものか否かをめぐって、社会は混乱し、しばしば「性格の弱さ」として処罰の対象にしてしまう。刑罰は治療の代わりにならないが、政治的には容易に正義の装いをまとうことのできる主張なのである。
5. スティグマの構図
薬物をめぐる議論には、さらに「われわれ」と「かれら」という二項対立が潜んでいる。薬物使用者は、道徳的にも社会的にも「普通の人間」ではないとされ、社会の辺縁もしくは外側に追いやられる。
とくに日本では、薬物使用者は「更生が難しい、あるいは不能な人間」として扱われがちであり、逮捕のニュースには「堕落」や「転落」といった言葉が並ぶ。スティグマは、個人の全人格を覆い隠し、治療や社会復帰の機会を難しくする。薬物依存を「病」として扱うと称しながら、実際には「罰」をもって対処するという矛盾が、その回復を阻んでいる。スティグマは社会的排除を永続させる装置であり、薬物政策の核心にある懲罰的論理と表裏一体となっている。
6. 薬物政策におけるダブルスタンダード
薬物に関する議論の感情的性質を増幅させるのが、処方薬や市販薬などの合法薬物と違法薬物の間に存在する明らかなダブルスタンダードである。
アルコールやタバコは依存性や健康被害が大きいにもかかわらず、文化的・経済的理由から容認されている。もし「有害性」を基準とするなら、最も厳しく規制されるべきはアルコールであるはずだが、社会はそれを許容し、「違法薬物」だけを悪魔化している。
さらに、今の日本ではオーバードーズ(OD)の問題が深刻である。処方薬や市販薬の多重服用による「OD文化」がSNSなどで語られ、若年層を中心に社会問題化している。
とくに最近は、違法薬物を使用することの大きな不利益を回避するために、市販薬に手を出すケースが増えているといわれている。オーバードーズが単なる医療事故ではなく、その背景には社会的孤立・心的外傷・精神的疲弊などが存在すると理解されるようになっている。つまり、オーバードーズは、単なる「薬の飲みすぎ」ではなく、心の叫びとその社会的サインなのである。
このような合法薬物と違法薬物の政策的な不均衡は、薬物政策が科学的根拠よりも感情と政治的利害によって動かされていることを示している。
また、禁止法そのものが新たな害を生むというパラドックスもある。密売組織の拡大、暴力の増加、刑務所の過密化、国家予算の浪費など、これらはすべて禁止政策の好ましくない副産物である。薬物の害は、薬物そのものよりも、禁止によって作り出された社会的条件によって増幅されているという面がある。
7. まとめ―犯罪問題から健康問題へ―
薬物をめぐる感情的対立は、道徳・政治・自律・スティグマ・政策の矛盾が重層的に絡み合った結果である。問題の核心は、薬物そのものではなく、それをめぐる「恐れ」や「嫌悪」を社会がどのように扱ってきたかにある。薬物を悪として断罪することは容易だが、それでは依存や貧困、社会的排除といった現実の痛みを解決することができない。
必要なのは、懲罰から理解へ、否定から受容へというパラダイム転換であり、薬物問題を犯罪問題としてではなく、健康問題として見る視点である。薬物使用をめぐる感情を静める唯一の道は、データと経験に基づく理性、そして苦しむ人びとへの共感を政策の中心に据えることである。社会が「正義の怒り」ではなく「理解の努力」を選ぶとき、初めて薬物との戦いは終わりを迎えるだろう。(了)
すでに登録済みの方は こちら