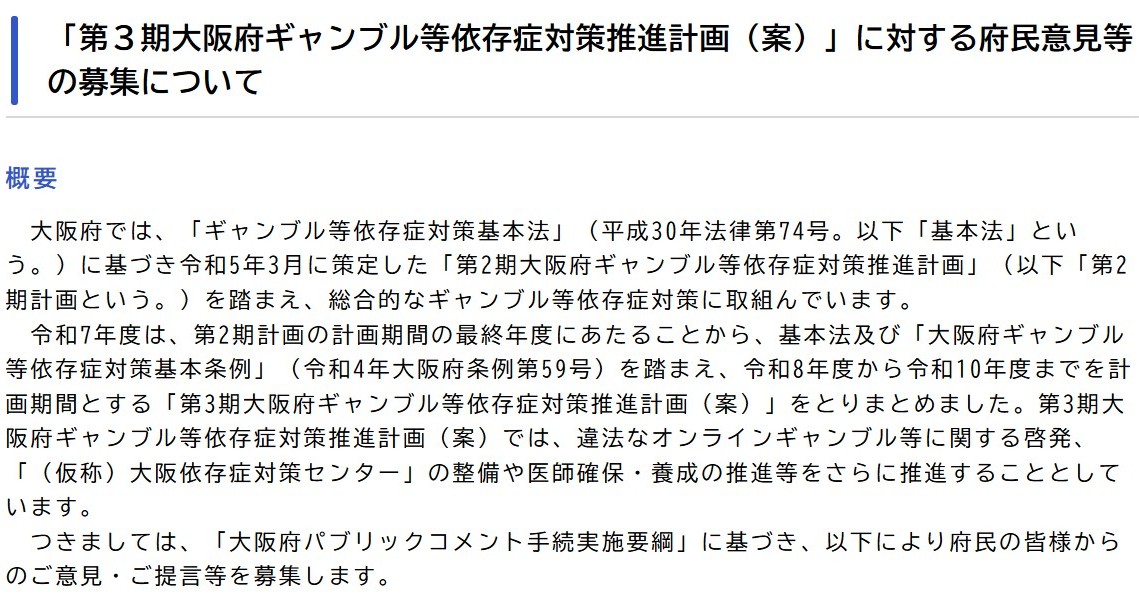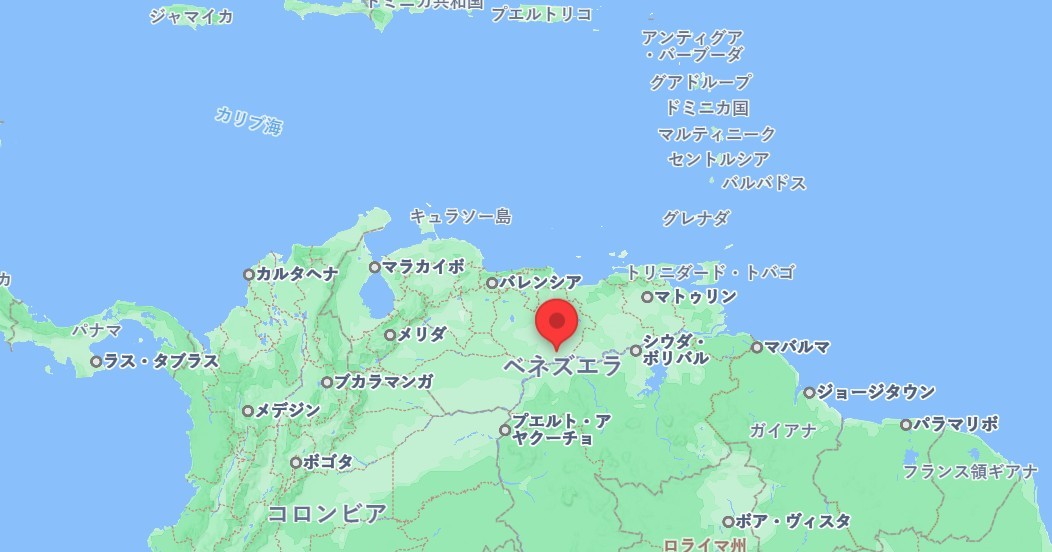薬物で精神を変容させること
はじめに―普遍と規制―
教室で学生たちに「薬物」について質問をすれば、「覚醒剤」や「大麻」、「ヘロイン」や「コカイン」などの答えが返ってくる。最近では「フェンタニル」という名前も聞くだろう。しかし興味深いことに、「アルコール」や「タバコ」について言及する者はほとんどいない。受講生の中にも、これら二つの薬物によって確実に何十年も人生を縮める者がいるにもかかわらずである。
世間では、「薬物」が〈合法〉か〈違法〉かの二つのカテゴリーに分けられる。それは、もちろん薬物に付与されている法的地位によるものであるが、薬物には死に至るものから一時的に変調を起こすにすぎないものまで、その有害性には段階的な濃淡がある。しかし、「薬物」の法的定義に関しては、そのような薬理的なグラデーションは本質的に関係がない。議論の出発点として、この点は確認しておく必要がある。
人類史をふり返れば、何かの薬物(植物)を用いて精神や意識の状態を変容させる行為は、特定の文化や時代に限定されない普遍的な現象であることが分かる。古代より、宗教的儀式や病の治療、あるいは日々の暮らしにおいて、精神に作用する物質は人びとの生活に深く根差していた。おそらくヒトの意識は、本来は生存に必要な情報を選別し、記憶することが本質的であるだろうが、精神作用物質は、その可能性を広げたり、超越的な領域へアクセスするための手段として機能してきたと思われる。
しかし現代社会においては、このような行為の是非をめぐる議論が錯綜している。特定の物質による精神の変容に対しては否定的な評価が下され、時には刑罰による厳格な法規制と社会的制裁の対象となる一方で、別の物質(薬物)は推奨あるいは黙認されている。
このように薬物による精神変容に対する評価がさまざまに分かれるのは、なぜなのだろうか。
1 医学的・生物学的観点―自律性の喪失―
薬物使用が否定される最大の根拠は、医学的・生物学的なリスク、とりわけ「依存症」による自律性の喪失にあるだろう。依存症(addiction)の語源だとされている「addictus」は、ローマ法における「債務奴隷」(自由意志が否定された状態)を意味していた。
米国国立薬物乱用研究所(NIDA)などが提唱する「脳疾患モデル」によれば、依存性薬物は脳内の報酬系を乗っ取り、生存に不可欠な活動(食事や生殖など)、つまり快感を上回るドーパミン放出を引き起こす。これにより脳の価値評価システムが歪められ、薬物摂取が生存における最優先事項へと書き換えられる一種の「学習障害」が生じるとされている。このような観点からは、薬物による精神変容は、脳の構造や機能を物理的に変化させ、人間性の核心である自己制御能力を破壊する病的プロセスだと考えられるのである。
さらに、過剰摂取による死亡や身体機能の低下、精神病の発症といった公衆衛生上のリスクも、規制を正当化する論拠となる。しかしながら、薬物使用者のほとんどは実は依存症には至らずに社会生活を営んでいるというデータも存在しており、薬理作用によるに物質的な有害性だけでは、精神変容そのものをタブー視する社会的な「悪」の構築を完全には説明しきれてはいない。
2 倫理的・宗教的観点―努力の倫理―
医学的な害以上に、薬物による精神変容に対する根源的な忌避感を形成しているのは、倫理的・宗教的な価値観である。ここには「薬学的カルヴァン主義」(Pharmacological Calvinism)と呼ばれる価値観が深く関係している。これは、苦労や努力を伴わない、安易な快楽や救済は疑わしいとするプロテスタントの倫理観である。
それは第一に、薬物によってもたらされる洞察(悟り)や多幸感は、人為的で偽りのものであり、現実からの逃避であるという見方である。安易な快楽は「魂の堕落」をもたらし、人間らしい感情や義務感を損なうとさえ言われている。
第二に、「努力の回避」に対して批判な見方がある。自己変革や苦痛の克服といった精神的成長のプロセスを化学物質に委ねることは、人間の主体性や道徳的価値を損なう行為だとして批判されるのである。
しかし、そもそも人間の意識や感情自体が神経伝達物質によって媒介されている以上、内因性の体験と化学物質による外因性の体験との間に、本質的な境界線を引くことは困難ではないだろうか。
3 統治と生産性―作られた善悪―
ある薬物による精神変容が「善(医療)」とされるか「悪(乱用)」とされるかの境界線は、物質の化学的性質よりも、その使用がなされる「社会的文脈」(Set and Setting)と「目的」にも依存している。
近代産業社会や戦時下において、「善」とされたのは「生産性の維持・向上」に資する精神変容であった。カフェインや、戦時下の日本やドイツで使用された覚醒剤(アンフェタミン)のように、覚醒を促し、恐怖や疲労を克服させて労働・戦闘能力を高める薬物は、戦争から多大な刺激を受けてきた。
対照的に、1960年代のサイケデリック・ムーブメントに見られるような、純粋な快楽の追求や、既存の社会秩序への疑問(脱構築)を促すような精神変容は、社会への脅威と見なされ厳しく排除された。つまりは、ダブルスタンダードである。精神科医であるトーマス・サズ(Thomas Szasz)が指摘するように、医師が処方する「処方薬(medication)」は正当化されるが、個人が自らの判断で苦痛を緩和しようとする「自己投薬(self-medication)」は「乱用」として断罪される。この区分は医学的というよりは、政治的・社会的な権力構造に由来する。
さらに、世界の薬物規制の構造に大きな影響を与えてきたアメリカの薬物規制の歴史が、人種差別の論理とも密接に結びついてきたことは見逃せない。アヘン規制は中国人排斥、コカイン規制は黒人への恐怖、マリファナ規制はメキシコ移民への敵意とリンクしており、薬物は「外部からの汚染」として、特定のマイノリティを管理・排除するための象徴として機能してきたのである。
4 パラダイム転換―ハーム・リダクション―
現代では、成人が他者に危害を加えない限り、自らの身体や意識に何を取り込むかを決定することは自由であり、幸福追求の一形態であるという考えが広がっている。
もちろん、これに対しては、依存性物質が自由意志そのものを生物学的に損なう可能性があるため、完全な自由放任は逆説的に個人の自律性を侵害するという反論もありうる。しかし、厳罰主義(ゼロ・トレランス)がむしろ使用者の孤立やスティグマを深め、健康被害を拡大させるという現実から、使用の中止よりも被害の最小化を優先する「ハーム・リダクション」のアプローチが世界的に広がっていることも事実である。
また、かつて「精神異常発現薬」として忌避されたLSDやシロシビン、ケタミンなどが、うつ病やPTSDの治療薬として再評価される「サイケデリック・ルネサンス」も到来している。これは、薬物による劇的な意識変容が、適切な文脈(医療)においては「治療的価値」を持つことを意味しており、精神を変容させることの医学的価値が見直されているのである。
結び
薬物で精神を変容させることが「悪である」という、普遍的な考えは存在しない。
生産性の向上や社会適応のため、ときには戦争のために薬物の介入が許容されてきたが、純粋な快楽や現実逃避は道徳や倫理に反するものとして非難される。また薬物使用には、個人の主体性を奪う(依存)か、主体性を拡張する(自己探求)かという軸があり、そこにはその管理が国家にあるのか個人にあるのかという政治的な力学が作用している。異質な精神状態や特定の集団を排除するために、薬物が象徴的に利用されてきたという歴史的経緯もある。
要するに、薬物問題の本質は、物質そのものの善し悪しにあるのではない。それは、人間が本質的に抱える「痛み」や「孤独」、そして意識を変容させたいという根源的な欲求に対し、社会がいかに向き合い、それをどう管理あるいは受容するかという、統治と倫理の問いに帰着するのである。現代におけるサイケデリックの再評価やハーム・リダクションの流れは、従来の硬直的な「悪」の定義を解体し、精神変容を人間の自由および治療の可能性として再統合しようとする試みなのである。(了)
すでに登録済みの方は こちら