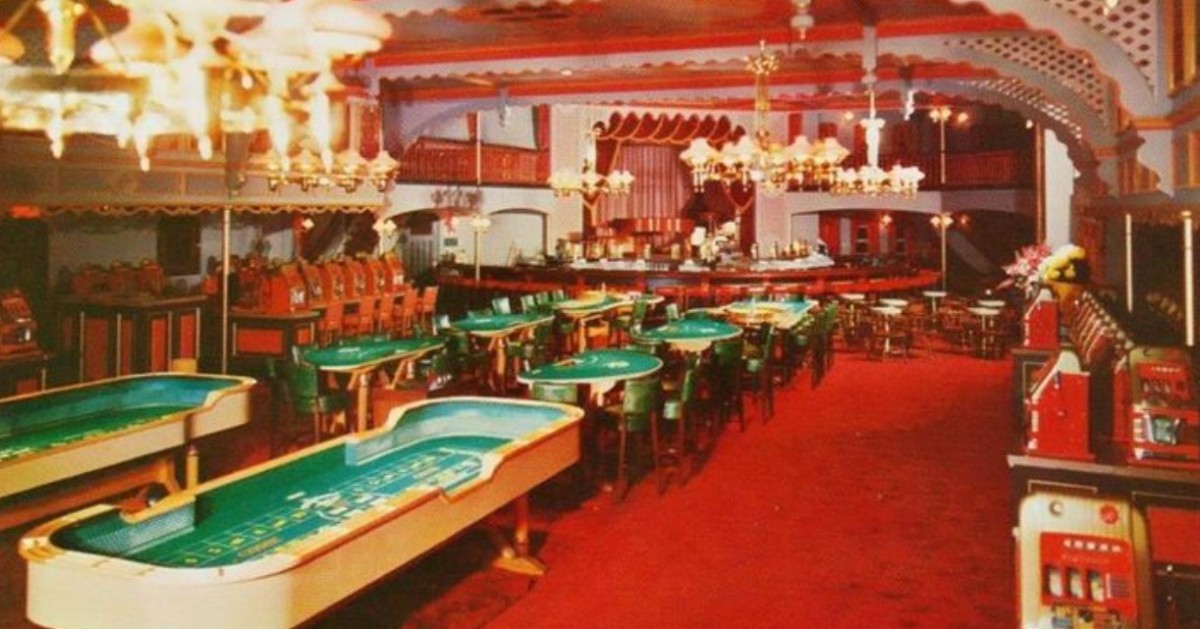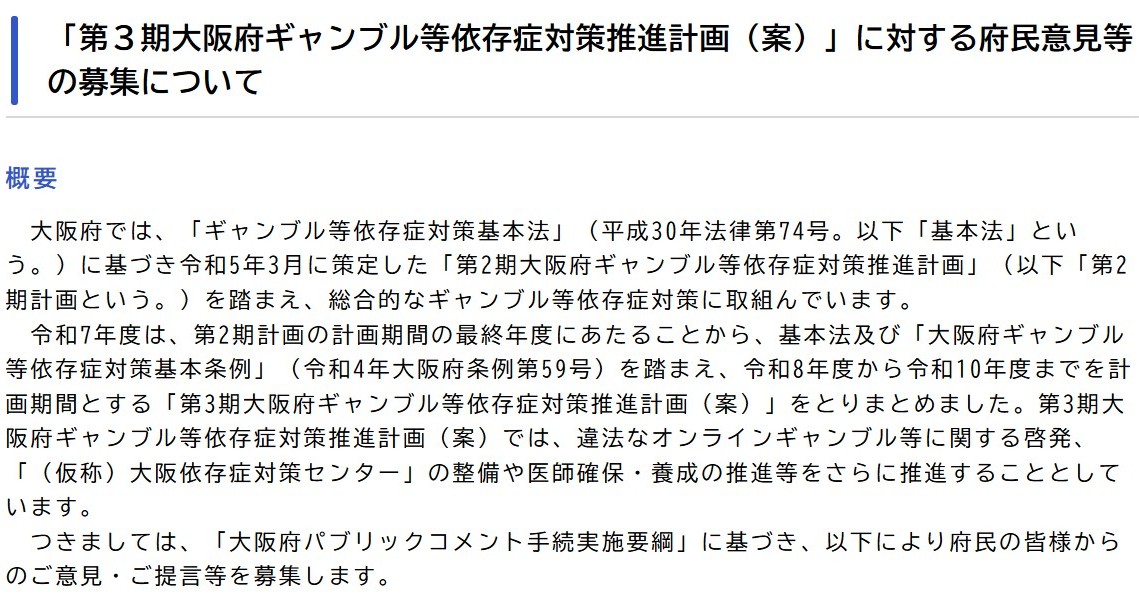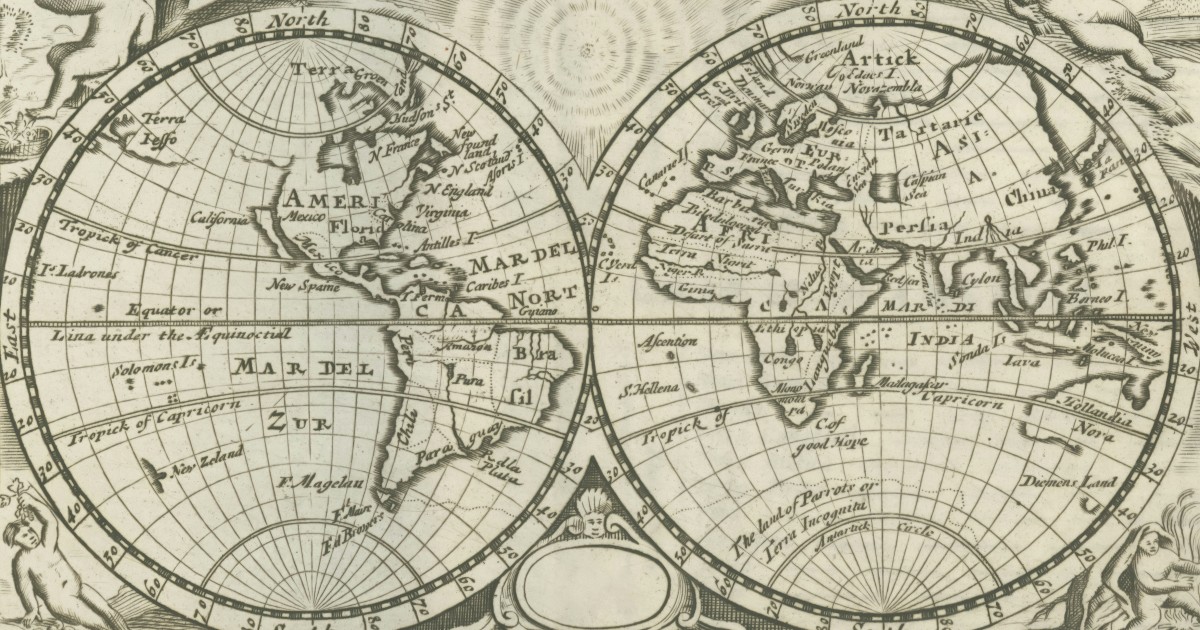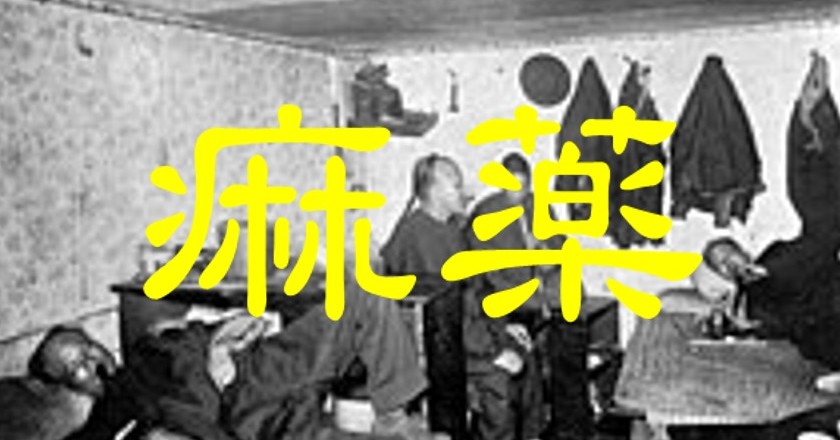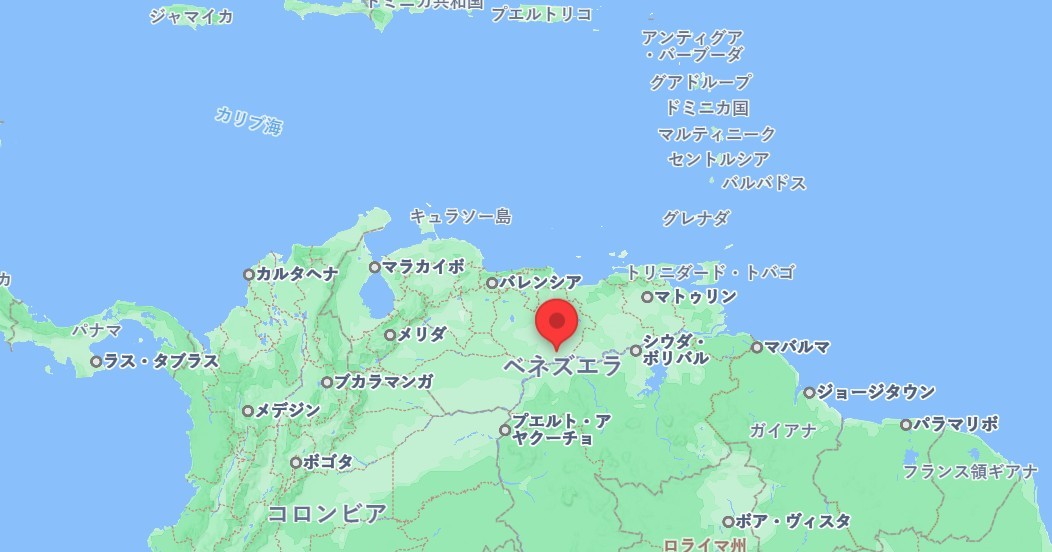薬物とは何か〈再論〉

1. 一般的な定義の難しさ
「薬」という字は、その次にどのような字が続くかで、その意味も、イメージも異なってくる。たとえば薬品と薬物である。
一般的な理解によれば、「薬物」とは、栄養補給や水分補給以外の生物学的機能に影響を与える化学物質である。その作用は、ヒトにとって有益なこともあれば有害なこともある。両方の性質を持つ場合もある。中でも、とくに精神機能(気分、知覚、認知、行動など)に影響を及ぼす薬物は、いつも議論の的になっている。
実際には、ある物質が薬物であるか否かを判断する明確な基準があるわけではなく、その定義は困難である。たとえば薬局方に収載されているか否かがひとつの基準とされることがあるが、これにはタバコ(ニコチン)の例をあげて不適切だと指摘されている。
日常的に摂取される物質も「薬物」として分類されることがある。砂糖や塩、チョコレートなどは、身体に強く作用し、精神機能や気分に影響を与え、依存症になる可能性もある。また、コーヒー(カフェイン)は多くの人が目覚めを良くする目的で摂取するが、これも薬物であり、身体依存を引き起こす可能性がある。アルコールやタバコも広く娯楽目的で使用される薬物である。
このように、「薬物」という言葉は、その科学的定義から日常的な使用、さらには身体が生成する化学物質に至るまで、非常に広範で解釈の余地がある概念なのである。
2.医薬品と違法薬物の違いは何か?
医薬品と違法薬物の違いをみてみよう。
医薬品と違法薬物の違いは、単純な科学的性質だけでなく、法規制、社会的認識、倫理的判断など、複数の複雑な要因が絡み合って形成されている。
2-1 目的による区別の困難さ
「医療用」と「娯楽用」の区別は困難であり、この曖昧さが薬物政策の議論を複雑にする。
たとえば、眠気覚ましのためにコーヒー(カフェイン)を飲む行為は、医療用なのか娯楽用なのか判別しがたい。しかし、同じ目的で覚醒剤(アンフェタミン)を使用した場合、もちろんそこには依存の強弱があるが、国家の厳しい対応が生じ、使用者は「犯罪者」とされる。しかしその場合、国家の厳しい対応には、殺人や強盗などの処罰の根底に損する応報的正当化とは異なる理由が認められる。
また、性的な目的のために薬物を摂取する場合や、摂食障害の治療薬なども、その使用目的によっては医療用と非医療用の境界線が曖昧になる例として挙げられる。たとえば「フォシーガ」という医薬品がある。これは、糖尿病や心不全などの治療に使われる錠剤であり、血液中のブドウ糖を尿に排出し、血糖値を下げる効果がある。また、心臓や腎臓への負担を軽減する働きもある。しかし、体重の減少も期待できるため、ダイエット目的で服用される可能性もある。製薬会社が将来、日常生活の楽しみを増やしたり、理想の体型を実現したりするために効果的な物質を開発すれば、この境界線はさらに曖昧になるだろう。
つまり、薬物の使用目的が医療用か非医療用(娯楽用)かという区別は、現在の薬物政策に期待されている大きな課題に耐えうるものではないだろう。
2-2 法的・政策的側面
2-2-1 禁止の根拠
多くの国で特定の薬物を違法とすることは、「納得できる理由がない限り、誰も罰せられるべきではない」という刑罰の正当化原則に反する可能性がある。刑罰は国家が個人に対して行い得る最も強力な制限だから、厳格な正当化基準を満たす必要がある。
「代理犯罪」としての薬物規制がいわれることがある。つまり、薬物禁止法は、薬物使用そのものを減らす目的だけでなく、薬物に起因した他の暴力事犯や財産事犯など、他の犯罪を予防するものとして機能することがあるといいうのである。しかし、このような考え方が一般的に正当化されるかについては議論がある。暴力事犯との関連でいえば、アルコールに起因する事件や事故がもっとも深刻なのである。
2-2-2 犯罪の助長
薬物禁止法によって薬物取引が違法とされると、そこに法的な救済手段がないため、薬物取引に関する暴力的な紛争が必然的に生じる。薬物禁止はむしろ潜在的で違法な利益率を高め、取引の過程で暴力や腐敗を生み出すことにつながる。つまり、取り締まりの強化は、その意図に反して闇取引の利潤を増やし、社会にとって好ましくない効果(犯罪)を増加させるという逆説的な効果をもたらす。これは「禁止の鉄則」と呼ばれている。
2-2-3 合法化・非犯罪化
大麻は、世界で最も広く使用されている違法薬物である。ヘロインやコカインに比べてその身体的な危険性は低く、そのため犯罪化する根拠が問われ続けている。
非犯罪化は、使用者やその介護者が援助を求める際の抵抗を減らし、犯罪者としての汚名(スティグマ)を払拭し、使用される薬物の安全性を高める(汚染物質や不純物の排除)など、いくつかの明確な利益をもたらす。
2-2-4 価格と規制
薬物が合法化された場合、税が課され、製造者には製品の使用による損害を補償する民事的な責任が生じるため、その価格は現在の闇市場の価格とは大きく異なってくる。しかしこれにより、ライセンスを受けた供給者が製品をより安全に供給するインセンティブを持つことになるというメリットがある。
2-2-5 「禁断の果実」効果
禁止されているからこそ、とくに青少年が特定の物質や行為に惹かれる「禁断の果実」効果が働く可能性がある。アダムとイブや、玉手箱を開けることを禁止された浦島太郎など、禁止されるとよけいに欲求が高まってしまうことをカリギュラ効果というが、禁止が解かれて合法化されることによって魅力が薄れ、薬物使用が実際に減少する可能性も指摘されている。
3. 社会的・倫理的側面
違法薬物使用者には強いスティグマ(汚名)が付随しており、非難され、社会的に恐れるべき存在と見なされがちである。依存症を「罪」や「性格的欠陥」が原因とみなすか、それとも「病気」とみなすかによって、社会の対応は大きく違ってくる。薬物使用を犯罪化することは、意図的にスティグマを作り出す行為であり、依存症を病気と主張しながら罰することは矛盾である。
成人が娯楽目的で薬物を使用する道徳的権利があるか否かという哲学的議論もある。自己の身体で起こることを決定する権利は、個人の基本的な権利と見なされ、国家が個人の快楽追求の価値を評価する権利はないという主張もある。社会には危険なスポーツやレクリエーション活動がたくさんあるが、もちろん処罰されない。しかし、薬物使用は処罰されるというのは、矛盾ではないのか。
多くの禁止論者は、違法薬物の娯楽的使用は不道徳であると主張するが、その根拠は不明確である。合法薬物と違法薬物の間に道徳的な観点からの正当な根拠はあるだろうか。脳の報酬経路に関わる神経伝達物質であるドーパミンは、薬物によって影響を受ける。しかし、ドーパミンが快楽のみを司るという単純な解釈は、さまざまな研究によって複雑化している。
医薬品と違法薬物の違いは、単純な化学的性質や健康被害の有無では説明しきれない。それは、社会の価値観、歴史的経緯、政治的・経済的利益、そして依存症に関する科学的理解が複雑に絡み合った結果なのである。その区別は「多数決だ」と喝破する依存症治療の専門家(松本俊彦医師)もいるのである。
4. 公衆衛生パラダイムへの移行
依存症は、最近では、慢性で再発を繰り返す脳の病気と見なされている。しかし、これは単に脳の化学物質への曝露だけでなく、使用パターン、使用者の過去の経歴、文化的背景、心理的・社会的要因など、複数の複雑な要因が絡み合って形成される学習障害であると理解されている。
このような理解を背景に、近年世界の薬物政策には、懲罰的アプローチから公衆衛生のパラダイムへと移行する動きがみられる。このパラダイムでは、薬物使用者は「犯罪者」ではなく、ケアが必要な「健康問題を抱えた人びと」と見なされ、政策の目的は薬物使用を抑制することではなく、危害を最小化し健康を促進することにあるとされる。
2001年にすべての薬物について、自己使用とそのための所持を非犯罪化したポルトガルのケースが有名である。結果的に、成人全体での薬物使用率には大幅な増加はなく、若年層ではその減少がみられた。また、薬物関連死や、非犯罪化前に比べ、(注射針の共有による)HIV新規感染者数が激減した。世界保健機関(WHO)や国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、このポルトガルモデルを「公共保健型アプローチの成功例」として評価している。
5. まとめ―「薬物」概念の拡大
最近では薬物の定義は、化学物質に限定されず、行動学的な観点からも拡張されている。たとえば、ギャンブル、セックス、食べ物、運動なども脳の報酬系を活性化し、強迫的な行動につながる可能性がある。総じて、「薬物」という言葉は、単なる化学物質の定義を超えて、人間の行動、社会規範、倫理、政治、そして歴史的背景と深く絡み合った複雑な概念となってきている。薬物政策に関する議論では、薬物に関するこのような理解の広がりを意識することが重要であると思われる。
すでに登録済みの方は こちら